「私が帰ってきたときは、スーパーに対しては完全にシャットアウト状態だったのですが、父も徐々に考えが変わってきたようで、『やってみたら?』と言ってくれました。
サンシャインさんは商品の販売だけではなく、四万十大豆のお豆腐で総菜を作りたいとおっしゃってくださって。うちのもめん豆腐と豆乳、おからで作った豆腐ハンバーグなどをお総菜コーナーで販売してくださっています。地元の事業者を応援する姿勢をすごく感じるので、ありがたいです」
「豆腐づくりがこんなに大変だと知っていたら継がなかった」
「どうしたらもっとお豆腐が売れると思いますか?」と筆者に逆質問してくるほど、のれんを守るために手を尽くす下田さんが家業に入ったのは10年前。離婚がきっかけだった。
「東京で子育てをするのは難しいと思って、息子と二人で高知に帰ることにしました。高知に戻るのなら、ほかで働くよりは家を手伝おうと思ったんですけど、父は自分の代でやめるつもりだったし、なにより重労働だから『女にできる仕事じゃない』と言われましたね。でも、できないって言われたことに腹が立って……」
しもだお豆腐店の長女として生まれながら、「私はただ豆腐屋に生まれただけで、一度も豆腐作りをしたことがなかった」という下田さんは、2012年、34歳のときに帰郷。豆腐作りを手伝い始めたが、「最初の2、3年は記憶がない」と振り返る。
しもだお豆腐店では、一晩水に浸した大豆を釜で煮て豆乳を作り、大きな桶に豆乳を75リットルとにがりを入れて固める。豆乳を運ぶことも一苦労ならば、力がないために豆乳とにがりをうまく混ぜ合わせることもできなかった。「大変さを知らなかったから手伝うって言っちゃいましたけど、他所で働いたほうが楽だったかもしれないですね」と下田さんは苦笑いする。
力が必要な製造工程は、下田さんと同時期に戻ってきた弟の泰功さんや3代目、男性の職人が担っている。けれど、それ以外の作業も「これまで朝から夜まで立ちっぱなしということがなかった」という下田さんにとっては慣れないことの連続だった。
「1つのコンテナに22丁のもめん豆腐が入るんですけど、それを何十箱と冷蔵庫に運んだり。お揚げを作るために、切ったお豆腐をフライヤーに入れて、出来上がったものからコンテナに入れていくんですけど、何時間もその作業を続けていると、だんだん手の力がなくなってきて、お揚げを持ち上げることができなくなってきます」
さらに、工場は、冬は極寒、夏は激暑。「手袋をしていても冷たいし、靴下を3重に履いても寒いんです。冷蔵庫のほうが暖かいくらいで、最初の冬はカイロを10個くらい貼っていましたね。それまでは一度もあかぎれになったことがなかったんですけど、手が真っ赤に腫れて、1週間と経たずにあかぎれになりました」。
















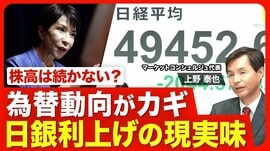















無料会員登録はこちら
ログインはこちら