ニュータウンは建物が老朽化、住民が高齢化して限界集落化などという報道もあるが、永山駅で電車を下りて諏訪地区、永山地区を歩いてみると思ったほど街は古びていないし、親子連れや公園で遊ぶ子どもの声も聞こえてくる。
諏訪地区では、老朽化した団地を民間マンション「ブリリア多摩ニュータウン」に再開発した街区や、再生事業、小学校跡地への集合住宅建設なども行われている。多摩市でも「多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画」が策定され、人工の横ばい、もしくは微減に対応した魅力あるまちづくりを進めているという。
「街づくり」は40年で終結
多摩ニュータウンの開発を中心的に進めた日本住宅公団は、1981年に解散し、その業務は住宅・都市整備公団に承継。2004年にその業務はさらに都市再生機構(UR)に移管された。

そして、都市再生機構が施行する多摩ニュータウンの開発事業は2006年3月末をもって終了。「多摩丘陵に計画的住宅市街地を建設し、良質な住宅を大量に供給することを目的」とした事業は、昭和40(1965)年の都市計画決定から約40年で幕を閉じた。
現在のニュータウン全体の人口は約30万人。
壮大な実験場として開発されていった日本最大級のニュータウンは、今後再び、高齢化、人口減少社会の実験場となっていくのだろうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

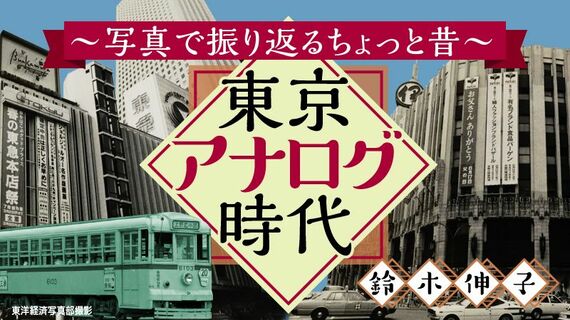






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら