「スシローが新型店を出したらしい…え、寿司じゃなくて天ぷら定食!?」 スシロー「次の一手は天ぷら」なぜ注目されるのか
「てんや」はチェーンの天丼屋としてよく知られているが、運営元であるロイヤルホールディングスの最新決算資料によれば現在の店舗数は182店舗あるものの、立地は全国16都道府県にとどまっており、全国にくまなく店舗を持っているとは言いがたい。
しかも、関西エリアについてはコロナ禍で一度撤退をしており、2023年にようやく再進出したばかり。2022年にはセルフレジなどを取り入れた「新型店舗」を東京に出店し、このフォーマットでこれから全国覇権を狙いにいく構えである。
他にも、丸亀製麺で知られるトリドールホールディングスが運営する「天ぷら まきの」や、サトフードサービスの「さん天」、「日本橋 金子半之助」などのブランドもあるが、いずれも50店舗以下程度の店舗数。
この背景には、天ぷらの「揚げ」技術の標準化・自動化が難しい点が挙げられる。油温や衣の厚み、提供タイミングといった変数が多く、品質の均質化が難しい。ある種の「職人」業が求められるため、拡大の中で人材の育成が追いつかず、スケール化が難しいのだ。
ただ、先ほども述べた通り、あおぞらはグループ企業での「揚げ技術」を生かしており、この難しさをクリアできる可能性がある。また、食材等についてもスシローの食材網を生かすのだから、スケール化の実現性は高いだろう。
ちょうどエアポケットのように空いた「天ぷらチェーン」の弱点を克服しつつ、その市場に挑む狙いが透けて見えるのだ。
「あおぞら」飛躍の可能性は?
というわけで、回転寿司の飽和や漁獲高の減少といった回転寿司側の事情と「グループシナジーの活用」、そして天ぷら業界の現状などを踏まえると、「天ぷら定食 あおぞら」の出店理由は鮮明になる。
さらに、今後日本では高齢化が進んでいくことは必至だが、天ぷらは高齢層に強く訴求するメニューとしても知られている。
博報堂の2024年度の調査では、天ぷらが好きと答えた人の割合は、他の世代に比べて60代以上が7%も高かったという。実際、筆者が「あおぞら」を訪れた際も、高齢者の来店比率が高かったことは述べた通りだ。
今後の日本において天ぷらは大きなマーケットになる可能性がある。現時点では1号店のみの展開である「あおぞら」だが、これらを踏まえると、近い将来に2号店、3号店と拡大していく可能性も高いのではないだろうか。
とくに郊外での展開には適性があり、駐車場を備えたロードサイド店舗としての強みも生きてくる。
さらに、個人的に思ったのは、この業態は都心でも十分に戦えるポテンシャルを持っていることだ。実際、揚げたての天ぷらを1000円前後で提供できる店舗でオフィス街のランチ需要を取り込めば、サラリーマン層にも大きく受け入れられるはずだ。都心と郊外の両軸で展開できるモデルになれば、全国制覇も夢ではない。
とくに大きなチェーンではその2種類のフォーマットがあることは必須条件だから、都心店の出店可能性がどれぐらい見込めるかにも「あおぞら」の今後は左右されるだろう。また、オペレーション面でどこまでブラッシュアップできるかという点も重要だ。
全国チェーンの少ない天ぷら業界で、「あおぞら」はシェアを拡大できるのか。今後の動向にも注目だ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

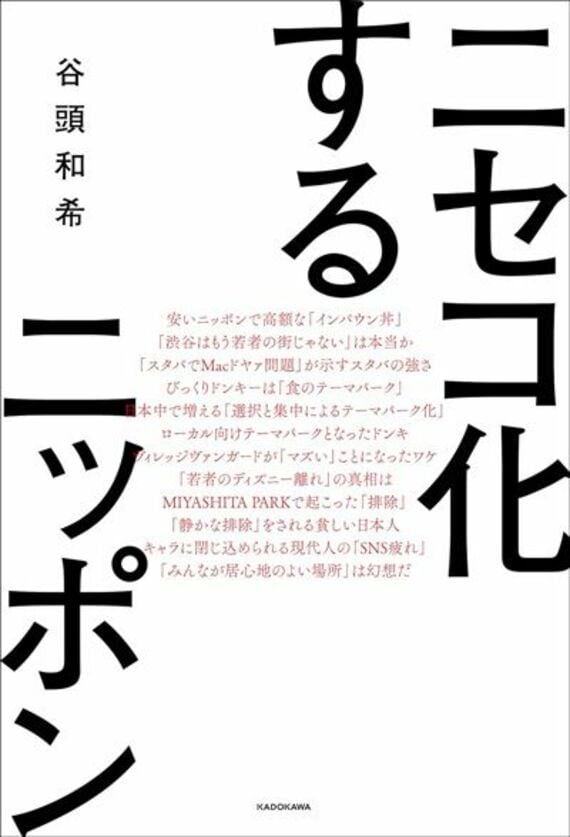































無料会員登録はこちら
ログインはこちら