発達障害の子どもの世話でパンクしないために、知っておきたい"逃げ道"…ケアを離れて休むことは、今や世界の「新常識」
国際条約として「障害者権利条約」が採択され、障害のある人をケアする家族を守って支援すること、ケアする人たちのことも社会全体で支えていくことが、項目として含まれています。
子育てや介護をしている人が、ケアしている相手から少しの時間でも離れて休むことは、世界の新しい常識です。
特性の強い子どもを他の保育者へ預けることには、気後れや不安がつきものかもしれません。さまざまな事情から、子どもと1人で向き合い続ける保護者もいます。
ですが、保護者だけの価値観で子どもを育てることは、その子どもにとってふさわしくないやり方に偏ったり、育ての「困り感」を抱え続けたりするリスクもあります。
「休憩上手」こそ「子育て上手」
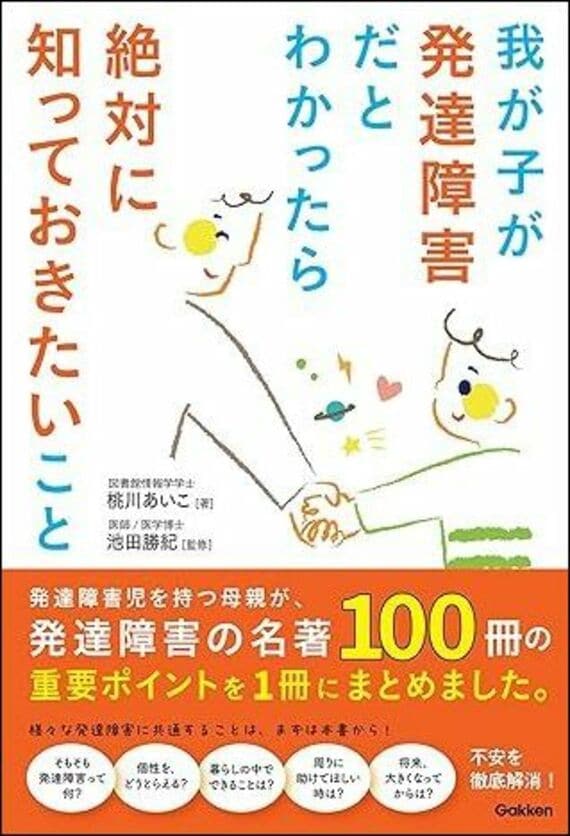
孤独な子育てから抜け出し、保護者にかかる心身的な負担を軽減するためにも、時には他の保育者の手を借りて、子育てから休憩をとることを勧めます。
自分とは違った保育経験のある人からは、子どもの特性について新しい見解を得られることがあります。
また、子どものことについてネガティブな考え方に引っ張られつつある保護者であるほど、子どもから距離をとる時間を確保して気持ちをリフレッシュしていくことも大切です。
特性のある子どもを療育施設へ連れて行ったり一時的に預けたりすることは、子どものケアであるとともに、保護者のレスパイトケアにもなります。
療育施設の中には、保護者の心のケアを重視しているところもあります。レスパイトケアを取り入れることは、保護者の「自分1人で頑張らなければならない」といったプレッシャーをやわらげる手助けにもなるのです。
保護者が一息つけるための、あらゆる工夫を探してみてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら