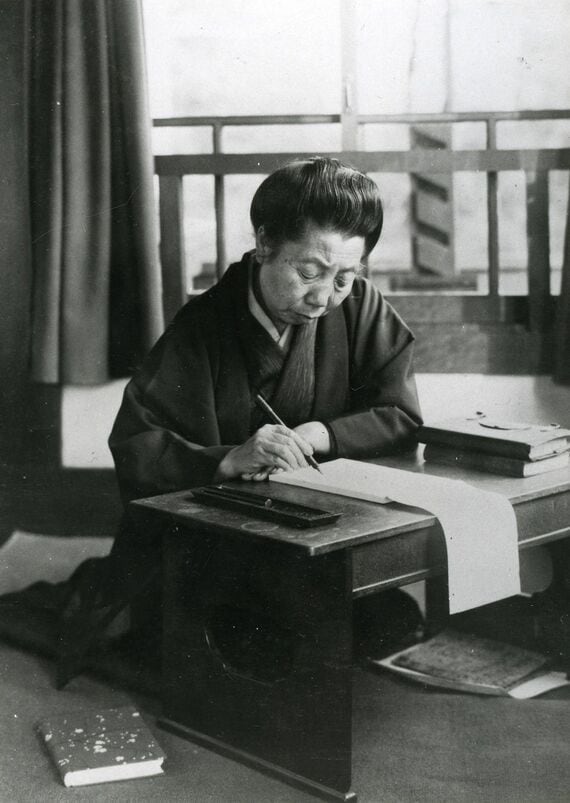
現在の自由学園は3万坪、東京ドーム約2個分という東京とは思えない緑豊かなキャンパスに、幼稚園から大学相当の学びを実践する最高学部(大学部)までがそろう。男女別学教育を行っていた中等科・高等科も昨年から完全共学化された。

昼食作りで学ぶこと
学園での生活は、とにかく人との関わりが濃い。日常生活からの学びを大切にしているため授業の進め方を見ても他校にはないユニークさがある。
例えば技術の授業では実際に壊れた自転車を生徒が持ち寄り、修理する。なかでもユニークなのは昼食の時間。中高それぞれの食堂で、3学年全員が集まって昼食を食べる。実はこの昼食を生徒自らが作っているのだ。

昼食作りは予算と栄養バランスを検討しつつ、献立を考えるところから始まる。高校のキッチンに足を運ぶと、家庭科を専攻する生徒らが男女一緒に厨房に立ち、270食近くを作っていた。
決まった時間に食事を提供するためには段取り力も必要だ。大きな鍋やフライヤーを前にテキパキと動く生徒たち。見守る教員に「もう少し急ごう」などと声をかけられてはいるものの、どの生徒も動きに無駄がない。

ビジネス書の中でも料理と仕事の段取り力を重ね合わせて紹介する本が時々あるが、彼らの動きを見ていると、その論も納得する。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら