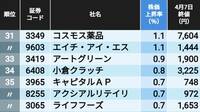アメリカ経済はスタグフレーションで済めば幸運。トランプ氏による自由貿易への攻撃は、その範囲と規模、細かい配慮の欠如という点で異例だ
こうした状況は、たとえ議会が減税措置で打撃を緩和しようとしても避けられそうにない。なぜなら、減税効果が表れるまでに相当なタイムラグがある上、低中所得層では関税による打撃の方が減税による恩恵を大きく上回るからだ。
さらに悪いことに、他の要因で経済の成長力そのものが損なわれる見通しだ。強制送還や移民の急減によって労働力の供給が弱まる一方、生産性の伸びは鈍化するとみられる。これにより、実質国内総生産(GDP)の成長率は昨年の2.5-3%から、およそ1%にまで落ち込むことになるだろう。
以上を踏まえると、スタグフレーション(景気停滞とインフレの同時進行)はむしろ楽観的なシナリオであり、より可能性が高いのは、インフレ加速を伴う本格的なリセッション(景気後退)に米経済が陥るという展開だ。
そうした中、金融当局に何かできることはあるのだろうか。通常であれば利上げによってインフレと闘うが、それでは不況を深刻化させることになる。パウエルFRB議長は、物価上昇が一時的なものであり、将来のインフレ期待に影響を与えないのであれば、利上げの必要はないかもしれないと示唆している。議長のこうした姿勢は投資家に一定の安心感を与えた。
しかし、FRBがその姿勢を続けられるかどうかには疑問の余地が大いにある。まず第一に、インフレ率は長期にわたって目標の2%を上回って推移している。仮に5年連続でインフレ率が当局目標を上回り、さらに加速するようであれば、インフレ期待が制御不能になるという重大なリスクが生じることになる。
次に、ショックの性質が問題だ。トランプ関税のように生産性を損なうタイプのショックは、インフレとインフレ期待により長期的な影響を及ぼす恐れがある。1970年代の2度のオイルショックを考えてみよう。2度のリセッションにもかかわらず、インフレは根強く残った。最終的に当時のFRBはボルカー議長の下、政策金利を20%に引き上げ、経済を深刻な景気後退に陥らせることでようやくインフレを抑え込むことができたのだ。