アメリカ経済はスタグフレーションで済めば幸運。トランプ氏による自由貿易への攻撃は、その範囲と規模、細かい配慮の欠如という点で異例だ
FRB自身の行動がインフレ期待に影響を与えるという点も重要だ。FRBがインフレ圧力を無視して経済成長ばかりを重視していると受け止められれば、その認識だけでインフレ期待は上昇することになる。
インフレ期待は、実際のインフレと闘うためのコストを左右するうえで極めて重要な役割を果たす。過去5年間と同様にインフレ期待がしっかりと固定された状態であれば、当局はあまり失業率を上昇させることなくインフレを管理することが可能だ。しかしインフレ期待が上昇してしまえば、犠牲率は急激に高まることになる。例えば1970年代のオイルショックのような状況では、インフレ率を1ポイント下げるためには、失業率が長期的な水準よりも2ポイント高まってもやむを得ないという厳しい調整が必要になる。言い換えれば、景気後退がFRBにとって唯一の選択肢になるということだ。
この非対称性は、米国経済が苦境に陥る中でFRBが非常に慎重な対応を迫られることを意味する。インフレ期待を刺激するような金融緩和を行えば、後になってより厳しく、より高コストな金融引き締めを余儀なくされることになるだろう。だからこそ筆者は、金融当局による救済について投資家は楽観的に過ぎると考えている。それどころか、リスクバランスと経済的不確実性の高さを考慮すると、当局の一段と慎重な対応こそが正当化されるのではないか。
成長鈍化、インフレ加速、動かないFRBという組み合わせは、株式市場にとって好ましい状況ではない。まさに勝ち目のない状況だ。企業が輸入コストの上昇分を消費者に転嫁すればインフレはより長期化し、金融当局はタカ派色を強めることになる。半面、価格転嫁ができなければ企業の利益率は縮小し、業績が圧迫される可能性が高くなる。諸外国・地域からの報復関税のリスクは言うまでもない。
債券市場で焦点となるのは短期金利の動向だ。現在、市場では年内100ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の緩和が織り込まれている。それが現実的になるのは(かつ正当化されるのは)、実際に景気減速が起きた場合に限られると筆者は考えている。今は2019年とは違う。当時はインフレ率が当局目標を下回っており、リセッションに対する「保険」として先回りの利下げを行う余地があった。現在、世界で最も影響力のある中央銀行であるFRBでさえ、対応の余地はほとんどない。
(ニューヨーク連銀の前総裁、ウィリアム・ダドリー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
著者:コラムニスト:William C Dudley "Bill"
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




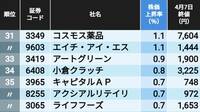


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら