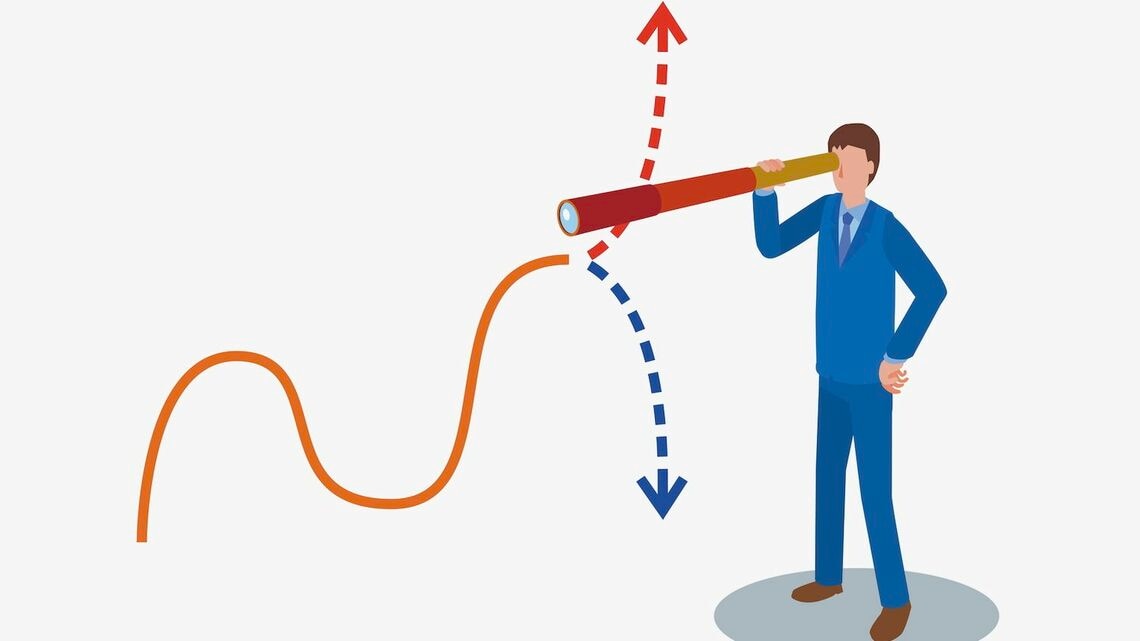
日本銀行調査統計局は9月9日、「『全国企業短期経済観測調査』の見直し方針」 というリサーチペーパーを公表した。日銀が四半期に1度実施している全国企業短期経済観測調査(以下、短観)の調査項目として「賃金改定率」を新設することなどについて「広く皆様からのご意見を募集する」という。
調査項目として、「正社員1人当たりの所定内給与の改定率」(前年比)の新設を「2027年前半に実施する予定」とされ、やや先の議論だが、人手不足問題が賃金・インフレ動向に与える影響に注目が集まる中で調査の拡充は歓迎されるだろう。
賃金統計について、日銀は春闘の賃金改定率に注目してきた。しかし、春闘は年1回の調査であるため、速報性に欠ける。短観における「賃金改定率」は半年に1回(6月、12月)行われる見込みであり、日銀の政策判断にも影響を与えるだろう。
先行きは結局「翌年度」のみに
調査の詳細については深入りしない(日銀の見直し方針はこちら)。一方で、当コラムでは短観の統計拡充のために実施された「予備調査」において得られた重要な示唆を紹介したい。
具体的には、企業は賃金改定率の長期見通しについて回答することに消極的であったという事実である。
すでに企業は長期の「販売価格の見通し」に回答していることを考慮すると、販売価格を決めてから賃金改定率を決めるという順序が一般的になっており、賃上げ⇒物価上昇という「連関」は弱いという現実が浮かび上がってくる。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら