「助産師を舐めるな」ーー彼女が起業した切実な理由 救えなかった"いのち"への悔しさが原動力、産後の母子をサポート、目指すは“現代の産婆”
岸畑さんはファイナリストとなり、LED関西のプロデューサー・井本達也氏や参加者たちの熱量に触発されて法人化を決意。
「助産師が活躍する社会をつくる。その先に、悲しいいのちのない未来を実現させたい」という思いから、「助産師とともに」という意味を込めて株式会社With Midwifeを2019年に設立した。資本金は、以前から起業のために貯めていた300万円を充てた。
コロナ禍で身動きが取れず、資金繰りに苦労しつつも、企業に専属の助産師をおく「顧問助産師サービス」を始め、2021年に法人向け伴走従業員支援サービス「THE CARE(ザ・ケア)」と名称を変更。
専属のウェルネスコーディネーター(助産師、看護師、保健師の国家資格を併有した医療専門家)3名が24時間365日、契約した会社の従業員に対して、健康やメンタル、子育てについてのサポートを行う。

ウェルネスコーディネーターとして働くのは、病院に就労できずに潜在化していたり、新しい活躍の場を求めていたりする全国の助産師たち。このサービスで、助産師や看護師たちの活躍の場が広がった。
ウェルネスコーディネーターで、現在同社の役員を務める竹﨑澪さんは「子育てって産後、退院してからが長い道のりですからね。病院で働いていた時には救えなかった人たちに届いている実感がすごくあります」と語る。
同サービスは、ロート製薬、タカラベルモント、伊藤忠商事など、福利厚生や社員のウェルビーイングに注視する約30社の企業が利用している。従業員の離職率や産育休の復職率の改善、メンタル不調に対する早期のケアなど、良い効果が生じているという。
産後の母子サポートを民間で行う意義
多くの人にとって「自治体が行うもの」という認識が強い産後の母子サポート。
民間サービスとして取り組む意義について岸畑さんは「自治体は予算が限られており、現状は特定妊婦などにアプローチする役割を担っています。助産院などの産後ケア施設を開業する人も増えていますが、運営する助産師は医療者であって経営者ではないので、事業の持続可能性が難しいのが実情です。こういった悪循環を解決するために、私たちが取り組む必要があるんです」と語る。




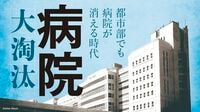




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら