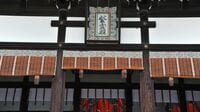「触れてはいけない存在」昭和天皇崩御が露わにした日本社会の構造

昭和天皇崩御のときの異様な雰囲気
奥泉 1989(昭和64)年の昭和天皇の崩御、あのときの異様な雰囲気はたいへん印象に残っています。戦後の天皇制について私たちが十分な理解をしてこなかった事実が露呈したと痛感しました。
このことを考えるにあたって、戦後昭和を3つの時期に分けてみます。オーソドックスな分け方だとは思いますが、①占領期から復興期(1945~1955年)、②高度成長期(1956~1973年)、③石油ショックからバブル期(1974~1989年)そして改元。
社会の3つの層──支配的エリート層、中間層、一般大衆層──について言えば、支配的エリート層は、吉田茂に代表されるような、日本人の宗家としての天皇家のイメージで象徴天皇制を捉え、大衆は、内実ははっきりしないものの、戦前に引き続く支持を天皇に対してしていて、これをGHQは占領統治に利用することになった。一方で戦前戦中に最も強く天皇崇拝を内在化していた中間層は、アンチ天皇に反転する傾向が生じた。
私は1956(昭和31)年生まれなので、物心がついたときには高度成長期のただ中だったんですが、3つの層の枠組みが一定のリアリティをもっていたのは、高度成長期くらいまでかなと思います。70年代初頭くらいまではかろうじてその枠組みにリアリティがあった。ところが70年代半ばくらいから、3つの層の区分けはそれほどくっきりしなくなっていった。