「国語の勉強」が仕事でも役立つと断言できる理由 「人を動かす」ために必要なのは"言語化力"だ
経営コンサルタントの新将命氏は、著書『自分と会社を成長させる7つの力』(アルファポリス)の中で「権力は人を指示命令で動かせても、納得させることはできない。そこで必要なのが権威の力である」といっています。
必要に応じて世界保健機関(WHO)や厚生労働省、日本小児科学会などの機関が公開している関連データを、わかりやすく教えてあげてもいいでしょう。
そのうえでの説明(ワラント)として、長時間にわたるゲームの使用による心と身体への悪影響や、これから待っている中学校、高校での生活といった近い未来像なども話し合ってみて、先に述べた「納得」に導くというプロセスを試みてください。
モチベーションを高める言語化
私は大学で教育学部の学生を相手に講義をすることが多いのですが、学生たちにいつもいっているのは、生徒から「なんで国語を勉強するんですか」と聞かれたとき、自信を持って答えられる人であってほしいということです。
教師自身が国語の重要性や意義を理解していなければ話になりません。母語である日本語の習熟が人生において大切であることは、既にここまで述べてきたとおりです。
カーネギーの言葉のとおり「人が自ら動きたくなる気持ちを起こさせる」ためには、相手を納得させる言語化力が必要です。
こうした考え方は、子どもを持つ親御さんにも通じることはもちろんですが、企業で部下や後輩がいるすべてのビジネスパーソンにも当てはまることです。
あるディベロッパーで働く若い方からお聞きしたことですが、まだ入社も浅い時期、ある都市開発チームのひとりに任ぜられ、地域の重鎮たちで構成される地元組合への説明会に足を運ぶ日々が続いたそうです。
精神的にも肉体的にも疲弊していたある日、数年後の街の誕生とそこで暮らす人々の生活が頭に浮かび、目の前の地道な資料作りとプロジェクトの遂行が、1本の線で結ばれたといいます。それが行動動機となって仕事を乗り越えられたのです。
自分がやっている仕事が全体のフローの中でどのような意味を持つのか、それ次第で結果がどう変わるかという具体像が、鮮明に描けているか否かで仕事へのモチベーションは格段に違ってきます。
「私たちのチームのデータ集積と分析次第で、クライアントの利益がこれだけ変わってくるんだよ」「君のここでの取り組みが、成果物に直接影響するんだ」といった明確な言語化によるフィードバックを丁寧に重ね、後輩たちが自ら動きたくなる気持ちを持つ手助けを心がけてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

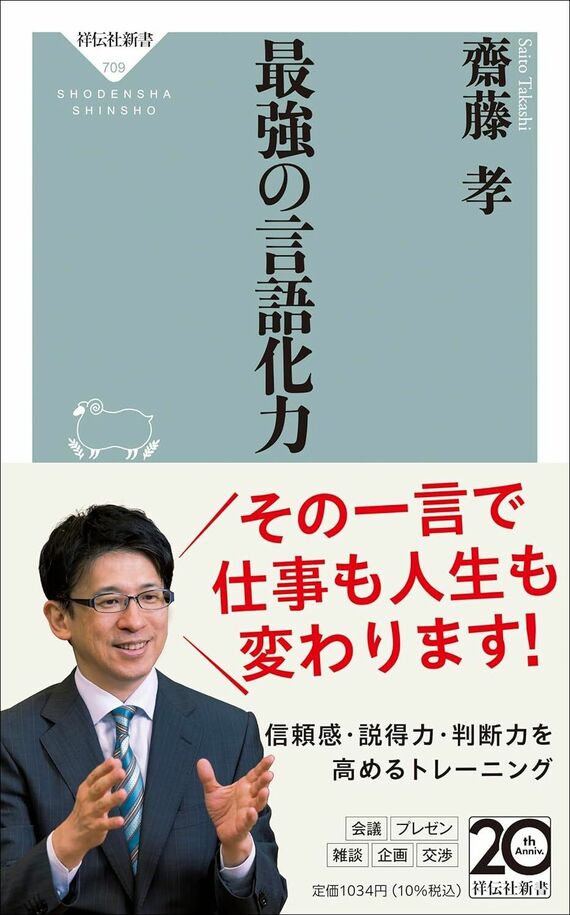






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら