「英語を話すゴール」に最短で向かう5つのルール 「とにかく話せば伸びる」という考えは間違い
一方で、多聴・多読は功を奏しました。その両方の経験を経て「英語学習はインプットが9割、アウトプットが1割」と強くオススメするようになったのです。
20年以上続けているから語れる多読成功のルール
ここからは多読するときのルールを紹介していきます。私が20年以上多読をするなかで気づいた、多読を習慣化して、英語を話すゴールに最短で向かっていくためのルールです。
基本的に、多読中は辞書を引かないほうがいいです。理由は大きく分けて2つあります。
①多読のリズムが崩れる
多読は楽しまないと続きません。度々辞書を引くことで読書が中断すると、リズムが乱れます。そうすると本の世界に入り込んで楽しむ、本来の読書の楽しさが失われてしまいます。
②文脈から意味を推測する力が育たない
分からない単語はすべて調べるほうがいい。そう思いがちですが、実は違います。一語一句意味を調べながら精読をしていると、英文を読んでいるときに文脈から意味を推測する力が育ちません。
例えば、TOEICのテストを受けていて、リーディングセクションのパート7で分からない単語が出てきたらどうしますか。辞書がないので、前後の文脈から意味や品詞を推測して、何とか解くしかないでしょう。
私が専門的に教えているIELTSはこれがもっと顕著です。複雑で難易度が高いパッセージが出題されるので、英語上級者であっても必ずといっていいほど未知の単語に遭遇します。精読しかしてこなかった人は、そんなときつまずいてしまいがちなのです。
精読に偏り、多読が足りていない方は、IELTSで5.5以上の壁をなかなか超えられない。実際、これまで5000人以上の学習者を見てきて、そう感じています。
普段の会話でも同じことが言えます。実際にネイティブとコミュニケーションを取るときは、リズム良くキャッチボールをするように話していきます。分からない単語が出てくる度に、辞書を調べるわけにはいきません。辞書に頼りっぱなしの勉強をしていると、こういうときにフリーズしてしまい、太刀打ちできなくなるのです。



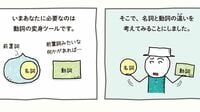



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら