「パワハラ認定」されかねない、上司のNG言動15選 本人の「自覚のなさ」がトラブルにつながる
図表1の要素を満たさなくても、図表2の6つの類型に該当する言動は、パワハラとされトラブルにつながります。また、企業で研修などを通じて不適切な言動を慎むよう注意を促しても、本人が無自覚のままそのような言動を行い、トラブルにつながるケースも見られます。
特に留意すべきパターンを以下に挙げます。
【①厳しすぎる指導】上司は部下の成長を考えて厳しく指導しているつもりでも、部下にとっては過度な叱責や圧力として受け取られる場合があります。
【②残業や休日出勤の命令】目標達成のために、部下に対して、必要以上の残業や休日出勤を命令してしまうことがあります。
【③成果主義の押し付け】部下の能力や状況を考慮せずに、成果を上げることを強く要求し、部下に過度のストレスを与えてしまうことがあります。
【④他の社員と比較する】「他の社員はこれくらいやっている」という比較を持ち出し、部下にプレッシャーを与えてしまうことがあります。
【⑤軽率なジョークやコメント】上司からの軽い冗談やコメントが、部下にとっては屈辱的に感じられることがあります。
「不適切な言動」が発生しやすい環境とは
こうした無自覚の不適切な言動の発生原因として、以下のようなものが挙げられます。
【①過去の経験と成果主義の風土】上司となる人の多くは、自分自身が過去に厳しい指導を受けた経験があります。そして、その経験が無意識に体に染みついてしまい、部下への厳しい指導が当然と考えるようになります。その結果、部下に対する厳しい口調や否定的な態度を、無意識に自分のなかで正当化してしまうことがあります。
また、成果主義の職場風土がある場合、上司が部下に過度なプレッシャーを無意識に与えてしまうこともあります。
【②無意識のバイアスと偏見】上司が特定の部下に対して、無意識のうちに偏見を抱き、不適切な態度を示すことがあります。これらのバイアスや偏見の多くは、過去の経験や価値観、個人的な感情に基づいています。その結果、他の社員と比較した不適切な発言や軽率なジョークを行うことがあります。
【③ストレスと余裕のなさ】上司自身が、職場でストレスを抱えているケースも少なくありません。このストレスが原因で、無意識に部下に対して厳しい口調や態度を取ることがあります。また、上司が時間に追われている状況では、業務を効率的に進めるために部下の意見を聞く余裕がなくなることもあります。その結果、いつのまにか上司と部下の関係が悪化し、不適切な言動が生じることがあります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

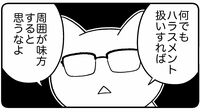





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら