「パワハラ認定」されかねない、上司のNG言動15選 本人の「自覚のなさ」がトラブルにつながる
職場の雰囲気を悪化させるようなネガティブな発言は、職場の士気を低下させる要因となります。上司がストレスや不満を発散するために無意識にネガティブな発言をしてしまうことがあり、それが職場全体に悪影響を与えることがあります。上司は、ポジティブな発言とコミュニケーションを心がけることが重要です。
部下に過度のプレッシャーをかけることは、ストレスを増加させ、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。また、上層部からの圧力を受けた上司が、それを部下に転嫁してしまうこともあります。部下に対する適切なサポートと目標設定を行い、部下のストレスを軽減させる必要があります。
部下に対して偏見を持って接することは、不公平感を生み、職場の信頼関係を損なう結果につながります。性別を理由として役割を分けることも偏見の一種です。上司は、偏見を排除し、部下の能力や業績を客観的に評価する努力が求められます。
チェックリストの活用方法
パワハラの防止は、会社全体で取り組むことが重要です。そのために、チェックリストを以下のように活用しましょう。
チェックリストを社内メールやイントラネットを通じて、上司の立場である社員に配付し、定期的にチェックしてもらい、自覚を促します。また、部下の社員にも自分の上司について、アンケートを行い、認識のズレが生じていないか確認します。部下へのアンケートは、「非常に多い」「多い」「ほとんどない」「ない」といった複数のチェックボックスを設けましょう。
社内研修を通じて、無自覚の不適切な言動の考え方やその影響について、社員に広く理解してもらうことが大切です。研修は、前述のアンケート結果を反映させた具体例を用いたグループワークが効果的です。
たとえば、アンケート結果から、「業務外の時間に頻繁に連絡をとっていないか」に問題がある場合は、『営業部の●●社員は、帰宅後の深夜に、△△営業課長から「〇〇の件、気になったので連絡した。折り返し待っている」といった連絡をメールで受けた。このようなことが続いているため、●●社員は、精神的にまいっている』といった事例を作成し、グループワークで改善策を発表してもらいます。
これにより、「業務外の時間に頻繁に連絡をとることは問題である」という考えが身につき、パワハラの防止が図れます。
・企業へのハラスメント対策研修やセミナー(厚生労働省・経済産業省の委託事業、各種団体など)の経験が豊富である。
・著書は、「ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本(日本実業出版社)」など多数。
・雑誌執筆は、企業実務(日本実業出版社) 、労務事情/人事の地図(産労総合研究所)など多数。
・厚生労働省パワハラ対策企画委員会メンバー等を歴任。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

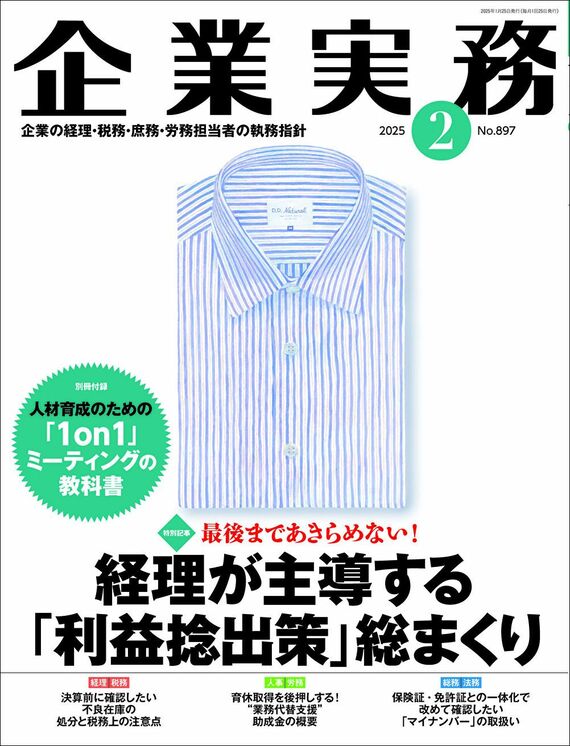
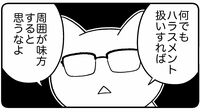











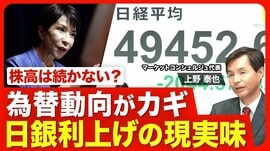
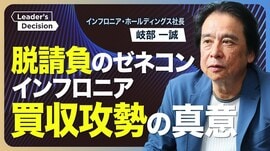






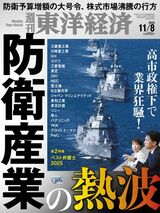









無料会員登録はこちら
ログインはこちら