インドでほぼ確でボラれる日本人「歩き方のクセ」 なぜ「騙しやすい奴」と思われてしまうのか
でも、分断されているから、お互いに簡単にわかり合えない(他者理解は容易ではない)ことも前提となる。そのため、うまく距離を調整したり、差異をわかりやすく表示したり、「わからないからわかろう」と努める姿勢が生まれる。
つまり、差異化して分断したのちに、互いの理解と、つながるための回路を形成していく社会。質問責めの裏にある構造が、少し見えてきた。
些細な差異をマスコットで表現する日本人
ひるがえって、日本はどんな社会だろう。「僕らって、みんな同じだよな」という同質性が出発点になっているように思える。他者との異質性はできる限りおさえ、輪からはずれることを嫌う。自分の意思を強く表明することも苦手だ。
一方で、ファッションや、方言や、髪型や、カバンにぶら下げたマスコットなどの些細な記号で、僕らは小さな差異の表明をし合っている。まったく一緒は、嫌なのだ。でもやっぱり「同質な我ら日本人」であることを前提としているから、無理に表現しなくても、伝わる(と考えている)。
他者を質問責めにするなんて、もってのほか。プライベートに踏み込むには、相当な時間を必要とする。パーソナル・スペースも広い。「空気を読む」は、「同質な私たちだから、わかるよね?」という暗黙のプレッシャーによって成り立っている。
荒っぽくまとめると、インド社会の関係原理を「差異の徹底的な顕示と異質性への対応・体系化」とするならば、日本社会は「同質性・単一性への傾倒と、それを前提とした個別の瑣末な差異化の力学」が駆動する社会だといえないだろうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


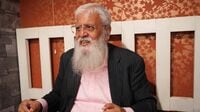






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら