ライター必見「上手な文章」に欠かせない要素3つ 「12歳の子が読める文章」を目指すべき理由とは
元来はノンフィクションも同じはずなのである。純粋に人間ドラマ、社会ドラマとして描けば、小中学生だって読めるものになる。
たとえば『聖の青春』は、内容はそのままで、ふりがなとイラストをつけただけで、小中学生を対象にした「角川つばさ文庫」のシリーズとして刊行されている。
著者の大崎善生さんは将棋の戦術や、将棋界の背景の説明を極力減らし、平易な言葉で青春ストーリーを書くことに徹している。だから、ふりがなさえつければ、小学校高学年から読めて、感動できる作品になっているのだ。
実は、本の対象年齢を下げるのは、読者層を広げるだけでなく、物語をシャープにすることにも役立つ。
書き手はできるだけストーリーから余分な“贅肉”を削ぎ落とし、鋭いものにしなければならない。本の対象年齢を下げれば、書き手は否応なく専門的な用語や小難しい解説を排除しなければならなくなる。これによってストーリーがより磨き上げられるのだ。
万人が読める作品にするというのは、文章のレベルを幼稚なものにするということではなく、作品を極限まで磨き上げ、読者の心にストレートに届くようにするということなのである。
優れた文章は五感に訴える
では、具体的に万人に届く文章をいかに書くのか。
この問いに、修辞技法を答える人も多いだろう。文章表現の勉強の一環で、比喩法、倒置法、反復法、擬人法、省略法といったレトリックの使い方を学んだ人もいるかもしれない。
ただ、何度も言うように、ノンフィクションで求められている文体は昔の文豪や稀代の名文家のような時代がかったものではない。そうした文体で評伝や企業ルポが書かれれば、読者は逆に噓っぽく感じるだろう。
現実を描くノンフィクションで大切なのは、読者に文章を通じてリアリティを感じてもらうことだ。この時に鍵となるのが、〝人間の五感を言葉にして表現する描写〞なのである。
描写というと視覚的なものに頼りがちだが、「嗅覚」「味覚」「触覚」「聴覚」「視覚」にまで拡張するのである。むせ返るような臭い、舌に残る濃厚な味わい、ヒリヒリとした手触り、鼓膜をつんざく音量、顕微鏡でしか見えない細かな視界……。描写の中に五感を表現する言葉を組み込むと、一気にリアリティが高まる。

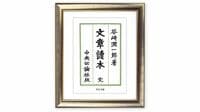




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら