門を叩かせると事情を知らない者が開けたので、車をそっと邸内に引き入れさせる。惟光が妻戸を叩き、咳払(せきばら)いをして来訪の旨告げると、少納言の乳母があらわれる。
「源氏の君がおいでになっていらっしゃいます」と惟光が言うと、
「姫君はお休みになっております。いったいどうしてこんな暗いうちにお出ましなのでしょう」どこかからの朝帰りのついでなのだろうと思いながら少納言は訊(き)いた。
「父宮のお邸(やしき)に移られると聞きました。その前に申し上げておこうと思いまして」と言う光君の真意をはかりかね、
「何ごとでしょう。こんな夜明け前ですから、姫君もさぞやはきはきお答えになることでしょうね」と少納言は冗談を言って笑っている。
光君はそれを無視して奥へと入ってしまうので、
「年長の女房たちがあられもない恰好で寝ておりますので」少納言はあわてて止める。
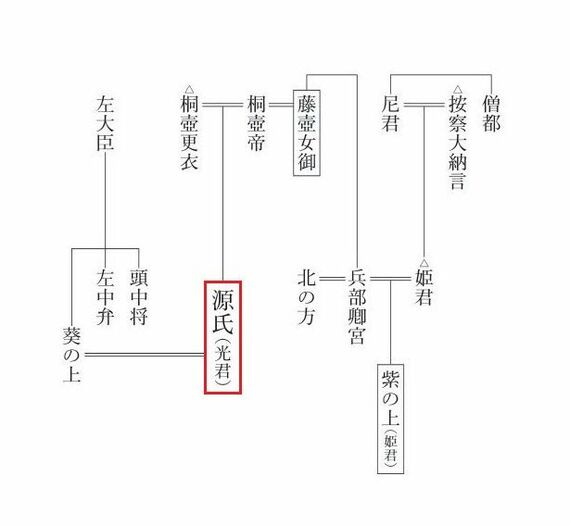
姫君の髪をやさしく撫で
「まだお目覚めではないでしょうね。なら、目を覚ましていただきましょう。こんなにすばらしい朝露を知らないで眠っているなんてことがあるものかしら」
と、光君は御帳台にすっと入ってしまうので、少納言は「ちょっと」と止めることもできない。何も知らずに眠っている姫君を光君は抱いて起こす。目を覚ました姫君は、寝ぼけながら、てっきり父宮が迎えにきたものだと思いこんでいる。姫君の髪をやさしく撫でて、
「さあ、いらっしゃい。父宮のお使いで参上しましたよ」と光君が言うと、父その人ではないとようやく気づいて姫君は驚き、恐怖を覚える。
「こわがるとは情けないな。私だって父宮と変わりはないよ」
姫君を抱いて御帳台から出てくる光君を見て、惟光も少納言も「いったいなんということを」と声を上げた。
「こちらにはしょっちゅう参ることもできずに気掛かりだから、気やすいところにお迎えしようと申し上げたのに、情けないことにあちらにお移りになるとのこと。そんなことになったらいっそうお話ししにくくなってしまう。さあ、だれかひとりお供しておくれ」
光君は言い、気の動転した少納言は、あわあわと言い連ねる。
「今日は、でも本当に都合が悪いのでございます。父宮さまがこちらにおいでになりましたらどのように申し上げたらいいのでしょう。そのうちいずれ、そうなりますご縁がありましたら自然とそうなりましょう、でも今はなんの用意もない突然のことですので、お仕えする私たちも困ってしまいます」
「ではいい。女房たちは後からでも来たらよろしい」光君は言い捨てて、車を呼ぶ。邸の者たちは一同驚きあきれて、どうしたものかと途方に暮れる。様子が変だと気づいて姫君も泣き出す。どうにも止めようがないと心を決めた少納言は、昨晩縫った姫君の着物を手にし、自分も適当な着物に着替えて車に同乗した。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら