「白浪の寄するなぎさに世を過ぐす海士の子なれば宿も定めず(和漢朗詠集/白浪の寄せる渚(なぎさ)に暮らす、家も定まらないいやしい身分で、名乗るほどのことはありません)」を女が引いたのに対し、「海士の刈る藻に住む虫のわれからとねをこそ泣かめ世をば怨(うら)みじ(古今集/海士の刈る藻につく『われから』という虫の名のように、自分のせいだと泣こう、世を怨まずに)」から、ならば「ワレカラ(私のせい)だね」
などと恨み言を言ったり、仲睦(むつ)まじく語り合ったりして、二人は時を過ごした。
惟光(これみつ)が光君をさがしあて、果物や菓子を届けさせた。ここで顔を出すと、やっぱりこうなったのは惟光の手引きかと右近に文句を言われるに違いないと思い、光君に近づくのはやめておいた。それにしても、女を連れ出して隠れ家にこもるほどの入れあげぶりが惟光には興味深く、光君をここまで夢中にさせるとは、いったいどれほど魅力的な女なのだろうと考えずにはいられない。自分がその気になればきっと我がものにできたろうけれど、光君にお譲り申したのだから、我ながらたいした度量の持ち主であるわい、などと不埒(ふらち)なことまで考える。
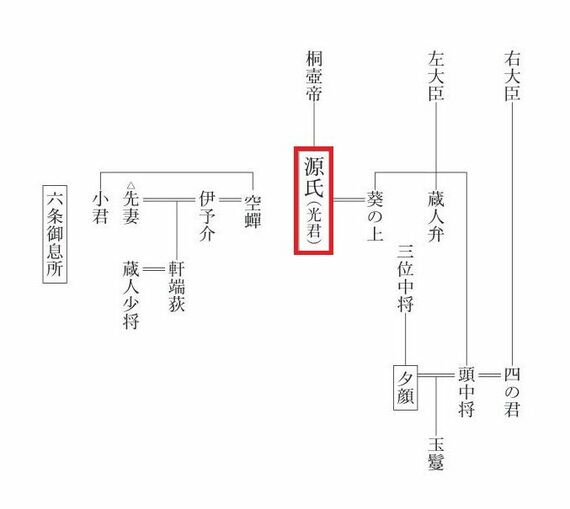
すべての嘆きの種を忘れ
静まり返った夕方の空を光君は眺める。家の奥のほうを女が気味悪がっているので、廂(ひさし)と簀子(すのこ)のあいだにある簾を上げて寄り添った。夕暮れのほのかな明るさに浮かぶ互いの顔を見つめ合う。こんなことになるなんて思いもしなかったけれど、すべての嘆きの種を忘れ、だんだん心を開いて打ち解けてくる女が光君にはいとおしかった。何かをひどくこわがって、一日中ぴたりとそばに寄り添っているのも、あどけなく思えて愛らしい。格子を早々と下ろし、灯をつけさせて、
「こんなに深い仲になったのにまだ名前を教えてくれないなんて、あんまりだ」と光君は恨み言を口にする。そして思う。
今ごろ父帝(ちちみかど)はどんなに自分のことをさがし求めておいでだろう、使いの者はどのあたりをさがしているのだろう。それにしても、たまたま知り合った、身分の高いわけでもない女にこんなに惹かれるなんて、我ながら不思議なことだ。六条のあの方も、さぞや思い悩んでいることだろう。恨まれるのはつらいが、どんなに恨まれても無理はない。申し訳ないという感情は、真っ先に六条の人を光君に思い出させた。男を信じ切って無邪気に座っている目の前の女をいとしいと思うと、あの人の、あまりにも思慮深く、こちらが気詰まりになるような重苦しさをなんとかしてくれればいいのにと、つい引き比べてしまうのだった。






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら