間違っていはいない。むしろ正しい主張だ。でも、自らのクビをかけてまで闘う必要があったのか。そもそも「貧困」をテーマにした本連載になぜ取材の申し込みをしたのか。重ねて尋ねる私に対し、カツヒサさんはしばらく考えた末、「非当事者支援は大事だと思うんです」と言った。
非当事者支援? 先をうながすとカツヒサさんはこう続けた。
「非当事者」が動かなければ解決しない
「水俣病をテーマにした『阿賀に生きる』というドキュメンタリー映画を観ました。その時、(患者以外の)非当事者が声を上げなければ、公害のことが広く知られることもなかったし、裁判闘争も続かなかったということに気がついたんです」
1992年に公開された『阿賀に生きる』は新潟水俣病をテーマにしたドキュメンタリー映画だ。監督をはじめとしたスタッフが阿賀野川流域に3年間にわたって住み込み、そこで暮らす人々の姿を描いた。
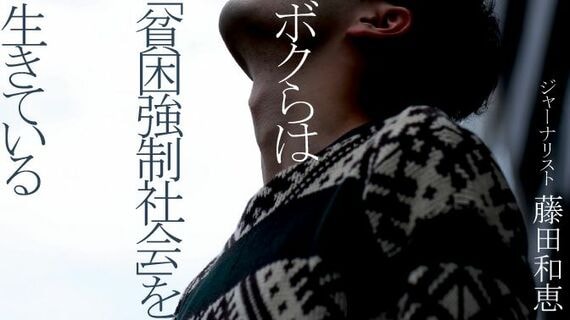
カツヒサさんの話が少し腑に落ちた。世の中には女性問題や沖縄問題など「〇〇問題」と称される課題が数多くある。ただ女性問題は男性側の価値観が変わることが不可欠だし、沖縄問題も国内の米軍専用施設の7割を負担させている沖縄以外の土地で暮らす人々こそが真剣に向き合うべき問題である。いずれも非当事者が動かなければ解決しない。貧困問題も、非当事者である自分こそが矢面に立つべきだと、カツヒサさんは言いたいのだ。
『阿賀に生きる』は社会正義を声高に叫ぶ作品ではない。農作業や餅つき、川漁、川舟造りなど流域の自然とともに生きる人々の営みを笑顔やユーモアを交えながら描く。それなのに病の過酷さや加害企業の非道さはひしひしと伝わってくる。
さらに不思議なことに「撮る側」と「撮られる側」の間の境界がときに見えなくなる瞬間がある。カメラの気配は限りなくゼロなのに、長期間にわたって暮らしをともにした「撮る側=非当事者」の強い意思を感じさせる。当時、国内外で激賞された作品である。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら