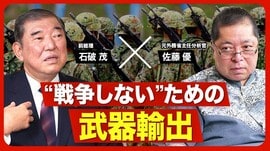問題は、この、肩の荷だ。
これが、イヤな話なのだ。
つまり怨念は、相続されるのである。
学歴という、ちょっとした家庭の事情や、国語算数の出来不出来や、あるいは試験当日の体調の良し悪しやら出題傾向の気まぐれで決定してしまうこのちっぽけな履歴が、一人の人間の一生を生涯にわたって支配し、のみならず、その学歴にまつわる怨念が、世代をまたがって息子にまで引き継がれていたりするわけなんだから。
父の怨念は、根の深いものだった。
それは、息子たる私が、引き継がざるを得ない、イヤな圧力で、家の中の空気を息苦しいものにしていた。言葉に出しては言わないものの、父は私に期待していた。大学に行ってほしいと思っていた。
おかしな話だが、私は、父が決して面と向かって「勉強しろ」と言わないところに、なんとも言えない圧力を感じていた。
深読みと言ってしまえばそれまでだが、私は、父が、その無頓着を装った態度の裏で、息を殺して息子の成績を見つめていることを知っていたのだ。
私たち親子は学問とはほど遠い人間であった
わが受験時代。暗い怨念の相克——イヤな話だ。
受験時代は受験時代として、ともかく、ワセダ大学に入るなり、私は、いきなり気落ちしてしまった。父の一生を台無しにし、幼い私にイヤな重苦しさを感じさせつづけていた「最高学府」の、思いのほかの空虚さに、気勢をそがれてしまったのだ。
いや、おそらく、空虚だったのは、大学よりも、むしろ私の方なのだろう。
怨念なんかで勉強したところで、何が生まれるはずもないのだから。
そういう意味では、父も私も、間違っていたのだ。
学問の府であるべき場所に、不純な憧憬や敵意や呪詛(じゅそ)を抱いていた私たち親子は、学問とはほど遠い人間であった。
そのことは認めよう。
学問を志して大学に入った人間は、あるいは自分の求めていたものを手に入れることができたかもしれない。
しかし、いったい大学にやってくる人間の何人が学問なんかをしにやってくるというのだろう。
私は、見たことがない。
いまでも折りに触れて思い出すのは、ワセダに入ってから知り合った、学歴に怨念を持たない人々の得意満面な姿だ。
私は、自分が彼らの仲間だとは到底思えなかった。
私は父の劣等感を相続していたのだろうか。
それとも、彼らの方が、どこからか人を人とも思わぬ気質を相続してきたのか?
いずれにしても、なんということもなく勉強して、何の疑問もなく優秀な成績で大学に入って、自分がエリートであることについていささかの疑念も抱いていない人々と、私は、どうしても打ち解けることができなかった。
この話は、稿を改めて書くことにしよう。
イヤな話になるだろう。
だって、イヤな連中の話なんだから。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら