雷が鳴った。二美子の頭の中で、である。
「え?」
「実はさっきまでここに座っていた女の人も」
「ルールが守れずに?」
「はい……彼女は亡くなった旦那様に会いに行ったのですが、ついつい時が経つのを忘れてしまったのでしょう……気がついた時にはすでにコーヒーは冷めきってしまい」
「……幽霊に?」
「はい」
冷静に返事をする数を見て、想像以上にリスクが高い、と二美子は思った。
過去に戻るためにめんどくさいルールはたくさんあった。幽霊がいて、呪いにもかかったが一時的なものだった。
だが、今度の話は少しわけが違う。過去に戻る事はできる。できるが、その制限時間はコーヒーが冷めきるまでの間だという。熱々のコーヒーが冷めきるまでに何分かかるのかはわからない。だが、そんなに長くはないだろう。とはいえ、苦手なコーヒーでも飲みきれない時間ではない。だから、ここまではいい。だが、飲みきれなかったら幽霊になるとなれば話は別だ。過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらないとしても、リスクはない。プラスではないが、マイナスでもない。しかし、幽霊になるのは間違いなくマイナスである。
二美子の心はゆれ動いた。懸念される事はいくつか思い浮かんだ。一番怖いのは数が淹れたコーヒーがものすごくまずかった場合だ。コーヒー味ならまだいい。もしも、激辛コーヒーとか、わさび味のコーヒーだったら、飲みほすなんて、できるわけがない。
まさか、考え過ぎだ。二美子は、一瞬よぎった不安をかき消すように頭を振った。
「とにかくコーヒーが冷めないうちに飲みほせばいいのね?」
「はい」
二美子の心は決まった。というか、少し意地になっていた。
数は静かに立っているだけである。「やっぱりやめます」と言っても顔色ひとつ変えないだろう。
「コーヒーが、冷めないうちに……」
二美子は、一度目を閉じ、固く握った拳を膝の上に置き、精神を統一するかのように鼻から大きく息を吸い、
「……いいわ」
と、答え、
「コーヒー……淹れてちょうだい……」
と、数の目を見て、力を込めて言った。
数は小さくうなずくと、トレイから銀のケトルを右手でゆっくり持ち上げた。数は伏し目がちに二美子を見つめると、
「……では」
と、一言仕切り直し、
「コーヒーが、冷めないうちに……」
と、ささやいた。
数はゆっくりとした所作でカップにコーヒーを注ぎはじめた。何気ない仕草ではあったが、一連の動きは美しく、儀式めいた崇高さが漂った。
カップに満たされたコーヒーからゆらりと湯気が立ちのぼったかと思うと、その湯気のゆれと一緒に二美子の座っているテーブルのまわりがゆらゆらとゆがみはじめた。
二美子は怖くなって目を閉じたが、自分が湯気のようにゆらゆらとゆがんでいる感覚はさらに強くなった。
握りしめた拳に力が入る。このまま現在にも過去にもたどり着けず、煙になって消えてなくなってしまうんじゃないか? そんな不安におそわれながらも、二美子は五郎と出会った頃の事を思い出していた。
(1月2日配信の次回に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

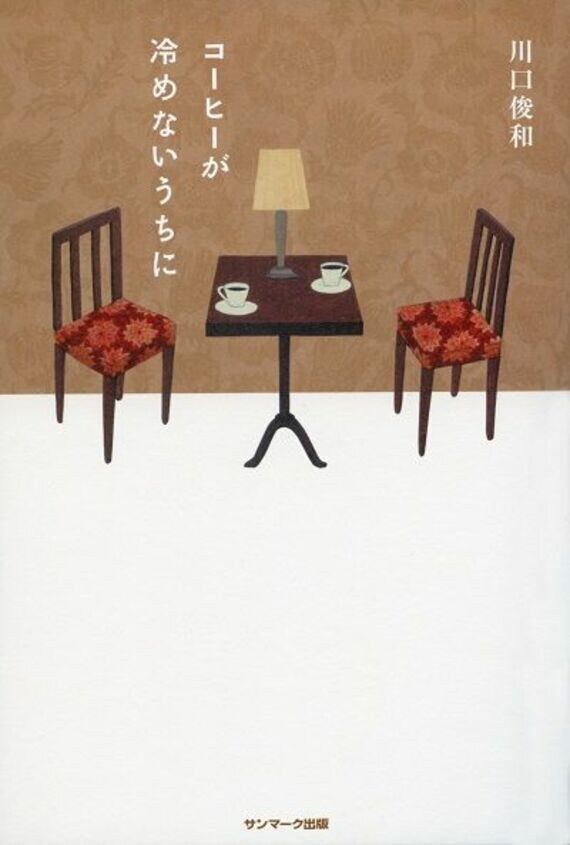





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら