1990年代半ば以降、携帯電話が一般市民に普及し始めた時期と、身元が判明しているのに引き取り手が現れない遺骨の数が増え始めたのは「軌を一にしている」というのが北見氏の見立てだ。人心が冷たくなったからというより、親族に電話連絡ができないことがハードルになっているのだ。
引き取り手が現れなかった遺骨は市の無縁納骨堂に移送される。お経も、聖歌も上げられない、無機質な堂に納められる。

それでは死者が浮かばれない、という観点で横須賀市が2015年から実施しているのが「エンディングプラン・サポート事業」だ。
頼れる親族がいない高齢者で、資産・預貯金が少ない人に限定し、低額(26万円。生活保護受給者は5万円から)で本人が望む弔い方を実現させるプランだ。本人は葬祭事業者に26万円を生前予納。市と葬祭事業者は本人が亡くなるまで電話かけや家庭訪問などで安否確認を続け、死後は葬儀社とともに市の職員が納骨まで見届ける。
2018年には終活事業の第2弾「わたしの終活登録」事業をスタートさせた。墓の所在地や遺書の保管場所、緊急連絡先などを本人が元気なうちに登録しておくことで、万が一の際、病院や警察などへの対応を市が本人に代わって担う。
親族の力は弱まっている
横須賀市が終活事業を推進するのは、市役所のロッカールームから無縁納骨堂へと移送されてゆく遺骨の数を、できる限り減らしたいという思いがあるからだ。
その人がどんな死生観を持ち、どのような弔い方をされたいのか、生前に確認しようとする自治体は横須賀市を含めて数えるほどしかない。「そんなのは親族がやるべき話で行政のやることではないと主張する役人のほうが全国には多い。でも、親族の力は弱まっている。本人の意思がわからないからと次々に無縁納骨堂に送り込んでいていいのか。それは行政の怠慢だと私は思う。もっと遺骨の声に耳を傾けないと」(北見氏)。
この国の、死者と向き合う姿勢が問われている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


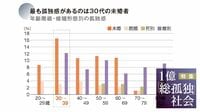






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら