日本人が知るべき戦争「飢餓との戦い」悲惨な実態 太平洋戦争末期の前線では米軍の攻撃より切実に
「おい、またかついでいくぜ」
「青隊だな、かわいそうに……」
芋畑に夜盗虫をとっていた兵隊たちがささやき合った、向こうの道を数人の兵隊が大きな箱に棒を通してかつぎ、静かに通り過ぎていった。いうまでもなく野辺の送り(死者を火葬場や埋葬地まで送ること)である。
青隊というのは内地の監獄の囚人部隊、正式な名前は「報国隊」で、海軍基地に陣地構築に送られてきたが、陸軍のように芋畑をもたない海軍関係者からは、とくにこの犠牲者がひどかった。昭和19年の末から20年にかけて約200名も栄養失調で倒れて、二大隊本部下の海岸墓地に送られていったものである。
行きも帰りもまったく同じ箱を担いでいた理由
「おや、あの箱また帰っていくぜ」
しばらくして、もときた同じ道を帰っていく箱をみて虫取りの兵隊たちがけげんな顔をして見送った。
「いったいこれはどういうことだ?」
「変だな、これで3回だぜ?」
行きも帰りもまったく同じ箱をかついでいた。何だかキツネにつままれたようなものだったが、あとでわかったことはこれが「通い箱」だった。
1人死ぬたびに、いちいち箱を埋めたり、焼いたりして新しく作っていたらたまらない。そんな資材は当時のトラックにはなくなっていた。仕方がなし墓地まで運ぶだけで、すんだらまたもち帰り、次の死体を入れていたのだという。
こういう中で、松本連隊の兵隊たちに栄養失調者が比較的少なかったのは、林田連隊長が熊本県天草の出身で、漁業に関心があった、天草は何といっても漁業の本場である。彼はここに来るとすぐこの漁業に力を入れたことと、
「腹がへってはイクサはできぬ」林田連隊長の口ぐせだった。だから自分でもいつもうまいものを食い続けたが、これで兵隊たちも動物タンパク質を比較的たくさんとれて助かったという説もある。もっともこれは将校の話であるが――。
もう1つ忘れられないのは、沖縄イートマン出身の現地召集者で、この人たちが先頭にたって漁労班で活躍したことであった。信州の山ザル部隊がそうやすやすと海で魚がとれるはずがなかったが、そのナゾは実はこの辺にあったことは間違いなかった。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

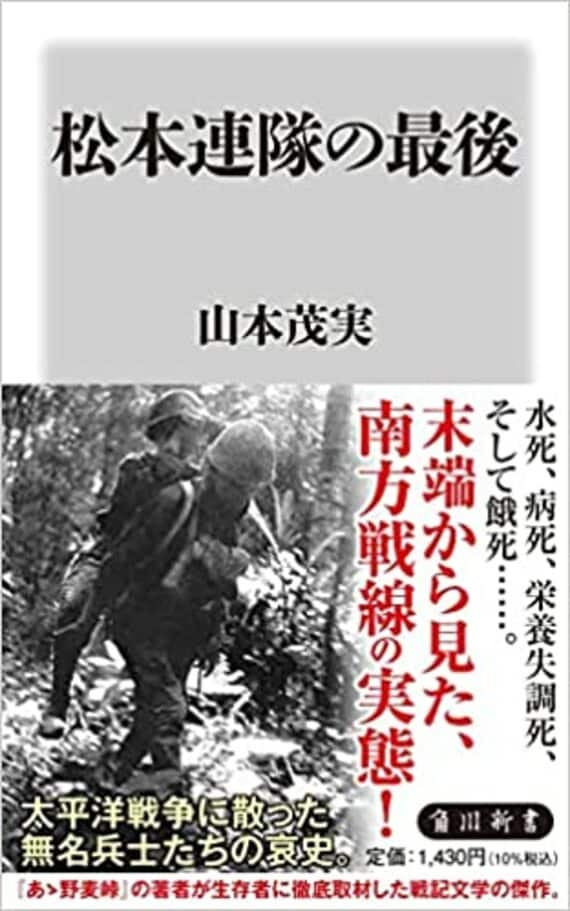































無料会員登録はこちら
ログインはこちら