「バイトだけの生活に焦りが募って、友達と自主制作の映画を撮るようになりました。制作費は当然、自己負担です。せっかく入ったバイト代の10万円が小道具代に、右から左へ消えていくこともザラでしたが、当時は『ここからなんとか名をあげるしかない』という気持ちでしたね。
大学の頃はいろんなバイトをしました。居酒屋、カラオケとか、本当にいろいろです。でも、生活はキツキツでしたね。3年になってから見つけた、たばこのサンプリングのバイトは比較的割のいいバイトでしたけど」
やがて3年生になった恩田さんは、就職に際し、上京を考えるようになった。
「もともと会社員になることには興味はなかったんですが、高校生の時から世話になっていた祖父母を安心させるために就職することにしました。映像業界は、今も東京が中心です。数少ない就職組の先輩たちに話を聞いていると、自分も『やはり東京に行くしかない』と思うようになり、夜行バスで面接に通いました。毎回いいところまでは進むのですが、いつも結果はキャンセル待ちの『次点』止まり。面接のたびに夜行バスの代金が3000〜4000円かかるのは痛かったですね」
そんな就活の末、映像広告を制作するベンチャー企業への内定が決まった。卒業制作もあって一文なしになってしまった彼に、内定先は「インターンで来てくれたら給料出すよ」との言葉をかけ、4年生の1月から働き始めることになった。
「東京で住むためのアパートを一室借りて、週1回ある出席必須の講義のために、関西に帰るという生活でした。その間、夜行バスの移動で家具を少しずつ運んで引っ越しました」
もちろん冷蔵庫や布団を運んだわけではないものの、それでも独特なエピソードである。
激務も人生は次第に好転していき…
しかし、入社した先はブラック企業だった。
「東京での仕事は始発から終電まで働くのがデフォルトで、繁忙期は土日も出勤。徹夜や会社に寝泊まりするのが当たり前で、毎月退職者がいました。社会人1年目は本当に仕事しているか寝てるかで、東京らしい思い出は一切ありません」
絵に描いたような、疲弊する映像の現場。つねに人が足らず、終わらない案件を大量に抱え、それなのに給料は安い……。恩田さんも、入社当初の手取りは14万円代だった。
「アパートの家賃が5万円だったのも痛かった。交通費が足りず、内見に時間を割けなかったんです。生活に余裕はありませんでした。多いときはロケ弁を30個持って帰って、1カ月食べつなぐこともありました。毎日同じ味です(笑)」

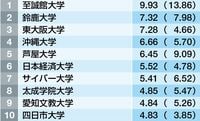
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら