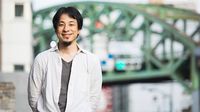「蔵元でありエンジニア」東大卒30歳の酒蔵改革 家業に入るまではエンジニアひと筋だった

「分からないからこそ飛び込む」
文系学生でありながらエンジニアになったのは「世界を知りたかったから」だった。就職活動を通じていろいろな業界を見ていく中で、もっとも目まぐるしく変化しているように映ったのがIT業界だった。
技術書なんて一生読むことはないだろうと思えるほど、それまでの西堀さんはおよそテクノロジーとは無縁。だからこそ開発者となり、仕事としてやらざるを得ない環境に自分を放り込むことで、世界を広げられるのではないかと考えたのだ。中でも「尖っていて個性的な人が多そう」という理由でワークスアプリケーションズの扉を叩いた。

エンジニアという仕事にどんな種類があるのかも知らなかった。自分がその後担う役割がシステムエンジニアと呼ばれることも、入社後に知った。
「教えない研修」として知られるワークスの半年間の入社後研修では相当に苦労したという。
「人に聞いてもいけないし、ググってもダメ。ただひたすらにコードを打ち込み、画面に現れる結果を見て、少しずつ理解できることを増やしていくといった内容で。半年かけてなんとか簡単なプログラムを提出し、晴れて配属となった先で、実務ではこんなに調べてもいいし、人に聞いてもいいんだ、そのことがこんなに幸せなことだったんだと知りました。
今にして思えば、どんなバグを前にしても根性で解決し続ける忍耐力を養う研修だったのかもしれません」

「西堀酒造」六代目蔵元・西堀哲也さん/1990年栃木県小山市出身。東京大学文学部哲学科を卒業後、株式会社ワークスアプリケーションズにてエンジニアとしてキャリアをスタート。2016年、明治時代から続く家業の酒造に参画(写真:エンジニアtype編集部)
配属先は原価管理システムの大規模開発チーム。モジュール化された管理会計の帳票出力部分などを担当し、ひたすらコードを書いた。言語はJavaとSQL。
やればやるほどできることは増え、仕事は楽しかったが、3年も続けるうちにサーバサイドだけでなく、フロントエンドの技術も知りたいと思うようになった。
2016年。世の中を見渡すと、SaaS市場が徐々に盛り上がりを見せていた。
西堀さんは、独立し、個人事業主としてWebサイトの受託開発を始めることを決意する。
レンタルサーバとCMSでできる簡単な仕事からスタートし、「ウイルスに感染したので駆除してほしい」といった細々した依頼も受けた。続けるうちにフロントのさまざまな技術を学び、加えてビジネススキルも自然と身に付いた。技術的には高度でなくても、組み合わせ次第で大きな価値を生み出せることもこの時期に学んだ。