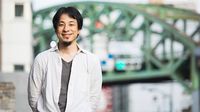「蔵元でありエンジニア」東大卒30歳の酒蔵改革 家業に入るまではエンジニアひと筋だった
しかしその年の冬、酒造りのピークの時期に実家の蔵人の一人が椎間板ヘルニアで酒造りを続けられなくなったという知らせが舞い込んだ。作業は3、4人で回しており、1人抜けるだけでもう回らなくなる。SOSを受けて、西堀さんは家業に戻ることを決めた。
「もともといずれは家業に入るつもりでいました。一度就職したのは、それゆえになおさら外の世界を知っておきたいと思ったから。どうせ戻るのであれば、現場の醸造の作業から入れるのはいいタイミングだな、と。
製造にはノータッチというパターンもあり得たわけですが、イチ蔵人として全工程を見たい、現場を知りたいというのは、僕がこだわった部分でした。頭だけで理解しようとせず、手を動かすことを重んじるのは、最初に入ったワークスという会社の好きなところでもありました」
とはいえ、酒造りに関する知識はこの時点でゼロに等しい。「なぜこうするのか」「なぜ急ぐ必要があるのか」といったことはまったく分からないまま、指示される通りに忙しく手を動かし続けた。
3月になり、ようやく最初のシーズンが終わったタイミングで、日本唯一の酒の研究機関である酒類総合研究所に研修に行き、そこで初めて理論的なことを学んで“答え合わせ”をした。まず飛び込んで手を動かし、徐々に世界への理解を深めていくやり方は、西堀さんの人生を貫く流儀のようだ。
非合理と向き合うための徹底した合理化

すべてを合理的に判断するエンジニアリングの世界とは対照的に、酒造りの世界は非合理の世界だった。当初は、目指す酒質から逆算するようにして要素分解していけば、ある種プログラミングのようにして理想の酒が作れるのではないかと考えていた西堀さん。だが、知れば知るほどそんなことは不可能だと分かった。
「各工程で起きていることが複雑すぎて何がどう影響しているのかが最新の研究でもよく分からない。蔵ごとに環境が違うから教科書通りにはいかないし、うちも含めた大半の酒蔵にとって1年に仕込めるのは100本に満たないから、ビッグデータ的なものも使えない。
それどころか迷信や願掛けのようなものがまことしやかに信じられていて、職人の経験則任せなところが強い。でも、理論的には到底信じられないような経験則が、結果としてどんな理論よりもうまくいったりする。そんな不可解な世界でした」
だが、その非合理なところが面白いと西堀さんは思った。絶対にコピペできない、この蔵だけの酒を作れるということを意味するからだ。
酒造りの世界でも今では蔵元の世代交代が進み、オープンに情報を共有してみんなで業界の水準を上げていこうという機運が高まっているという(まるでオープンソースのようだ)。となると、技術や知識は大きな差別化要因にはならない。
精米歩合を極限まで競うスペック競争の時代、モダンなラベルデザインでイメージ刷新を狙うデザインの時代を経て、次はストーリーの時代だとも言われる。だが、確たる答えはまだ出ていない。