結婚を機に、できることなら今の仕事を辞めてパート程度で働き、家のことを主婦としてやりたかったが、貰うお金が月4万円では生活していけない。自分の欲しいもの、必要なものも買えなくなるので、仕事はそのまま続けることにした。
そして、結婚生活がスタートしたのだが、浩はとにかくお金に細かい人だった。
「使っていない場所に電気がついていると、片っ端から消していく。朝、会社を出るときには、『待機電力がもったいない』と言って、テレビとかコーヒーメーカーとか家電のありとあらゆるコンセントを抜いていく。私がアロマをたいたら、『それって生活に必要? 電気代がもったいないし、僕は部屋中に匂いが充満するのは好きじゃないからやめてくれないかな』と言われました」
一緒にスーパーに買い物に行っても、値段を細かくチェックする。例えば納豆を買うときなど、いくつかあるブランドの中から、グラム数と値段を見て、一番コスパのいいものを選ぶ。
「休みの日に映画に出かけても、チケットを買うのは別々。100円ショップに行っても、自分が買うものを選んだら会計の列にさっさと並んでしまう。外食はほとんどしない。何か彼を見ていると、無駄遣いをすることは悪。貯金が増えていくのはいいけれど、減っていくことには強迫観念があるように思えました」
「僕らはごちそうしてもらえるの?」
あるとき、淑恵の大学時代の仲良し5人組の1人から、「結婚のお祝い会をしましょうよ。ご主人と出てきたら?」と連絡がきた。浩にそのことを告げると、彼は言った。
「それって、僕らはごちそうしてもらえるの?それとも会費制?もし払うとしたら、僕は遠慮しておくよ」
友人が、結婚のお祝いをしてくれるという会に対して、「ごちそうしてくれるなら行くけれど、払うなら行かない」という言葉に、淑恵は心底がっかりした。結局その会には、1人で参加し、当然のごとくみんなが淑恵を祝い、ごちそうしてくれた。
その会を終えて帰宅した夜、淑恵は、当てつけがましく言った。
「ああ、楽しかった。すっかりごちそうになっちゃったわ。久しぶりの本格的な中華料理は、おいしかった〜」
すると、浩が言った。
「なんだ、おごりだったのか。だったら、僕も行けばよかったな」
その言葉を聞いて、淑恵は、気持ちがスーッと冷めていくのを感じた。一緒に暮らしていくうちに、気持ちはどんどん離れていった。そして、ついに離婚を決意させる出来事が起こった。
実家の妹から、「お母さんが、キッチンで倒れて、救急車で運ばれたの」という電話が入った。母は80歳近くの高齢だ。心配と不安で病院に駆けつける身支度をしていると、そこに浩がやってきて、言った。
「手術とか入院とかになるのかな。もしそうなったときに、費用はそっちの家で持ってくれるよね。僕の親はもういないから、ウチには迷惑がかかることはない。淑恵の親のことだから、費用はそちらの実家で賄ってほしいな」
その言葉を聞いて、気持ちがストンと落ちた。お金の負担をフィフティフィフティにきっちり考えるのは勝手だが、親の命に関わる問題にまで、それを当てはめてくる薄情さに、怒りと諦めと、もう夫婦の縁を切りたいという気持ちが、一気に湧きおこった。
そして、10カ月の結婚生活は、翌月に幕を閉じた。


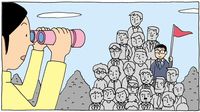




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら