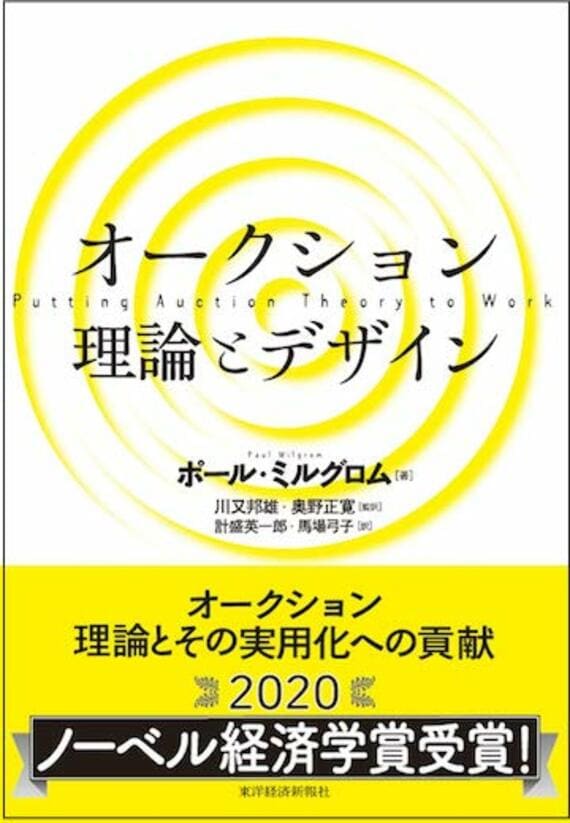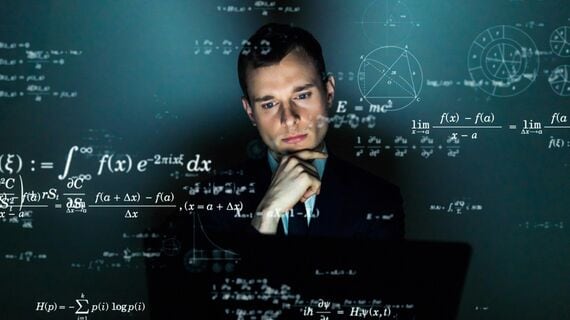
ホームラン級の論文や、新分野への貢献
安田:今年のノーベル経済学賞は、スタンフォード大学のポール・ミルグロム氏と、ロバート・ウィルソン氏(以下、敬称略)がオークション理論で受賞しました。
とくに注目されているのはミルグロムで、オークション理論については、メディアで多く紹介されたし、『オークション 理論とデザイン』をはじめ、彼の本は日本でも翻訳されている。さらに、ミルグロムはほかの分野でもホームラン級の論文を書いたり、新しい分野を打ち立てたりしているんですよね。
小島:僕はスタンフォード大学でミルグロムと同僚だったのですが、いくつか印象的なエピソードがあります。その1つが、僕に子どもが生まれた頃のこと。時間もないし、生産性も下がってしまって悩んでいたのですが、「自分も子どもが小さい頃は大変で、ちょっと論文の書き方を変えたんだ」と話してくれた。
どういうことかというと、「それまでの分野で論文を書くのが大変になったから、ほかのことを考えてそっちの分野の論文を書いてみたんだ」って。改めて見てみたら、確かにミルグロムが新しい分野ですごい論文を書いている時期が子どもの成長と完全に対応していて。
安田:わが子の成長に合わせて新分野に進出したということですね。それはすごい。ミルグロムは論文の数が多いんですよね。