人間国宝・神田松鯉が語る「講談と落語」の違い 似ているようで決定的な差がある
調子よくリズムをつけて読むようになると、その合間に調子をとる楽器が必要になります。それが「張扇(はりおうぎ)」です。「何が何して、なんとやら~何が何までなんとやら~」のあと”ポンポン”といった具合に、張扇で釈台を打つわけです。

落語家は扇子と手ぬぐいを持ち、座布団に座ります。講談師も扇子と手ぬぐいを持ち、座布団に座りますが、同時に釈台を置き、張扇というもう一つの道具を持つところが特徴です。この張扇は開きません。打つためだけの道具です。
落語は「会話」で話が進みますが、講談には「説明」が加わります。
たとえば、落語の場合、
「おい、八っつあん! あそこに何か白い物がチラチラしていねえか」
「ああ、なんだろう」
と会話の掛け合いで進展していくのですが、これが講談になると、
「道の先をずっと見渡すと何か白い物が揺れているように見える。熊五郎は八五郎の肩をたたき、『おい、あそこを見ろ』と指さしました」
となります。このように、台本でいうところのト書き、つまり説明を読むのです。
時代や日時、季節や街の景色まで明確に語る
講談は、軍記物語などに注釈を付けてわかりやすく読み聞かせる芸ですから、説明が多く混じります。落語に比べ、登場人物や場面の転換も多いですし、人物の身なりや来し方(過去)、時代や日時、誰がどこへ向かったのか、季節や町の景色などまで明確に語ります。
たとえば『赤穂義士伝』一つをとっても、冒頭から説明で始まります。
「元禄十五年十二月十四日、会稽山に越王が恥辱をそそぐ大石の山と川との合言葉末代めでたき武人の亀鑑(かがみ)……」〝ポンポン〟といった具合に。
ただ読むだけではありません。先に述べた修羅場調子に張扇でリズムをとりながら調子よく読みます。説明部分こそ、これぞ講釈という醍醐味を味わえるところです。
一般的には、講談は説明部分と会話部分が交互に入るのに対し、落語はほとんど会話部分だけで展開しますから、それが両者の大きな違いでしょう。また、創作性が濃い落語と違い、講談は史実に基づいたノンフィクションが中心で、筋のある物語になっていることも説明部分が多くなる要因です。
さらに、講談の説明部分は文語体で書かれていますから、落語に比べると「かたい」「わかりにくい」ということはあるでしょう。そこで現代の講談師は皆、なるべくわかりやすく説明するように工夫をしております。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

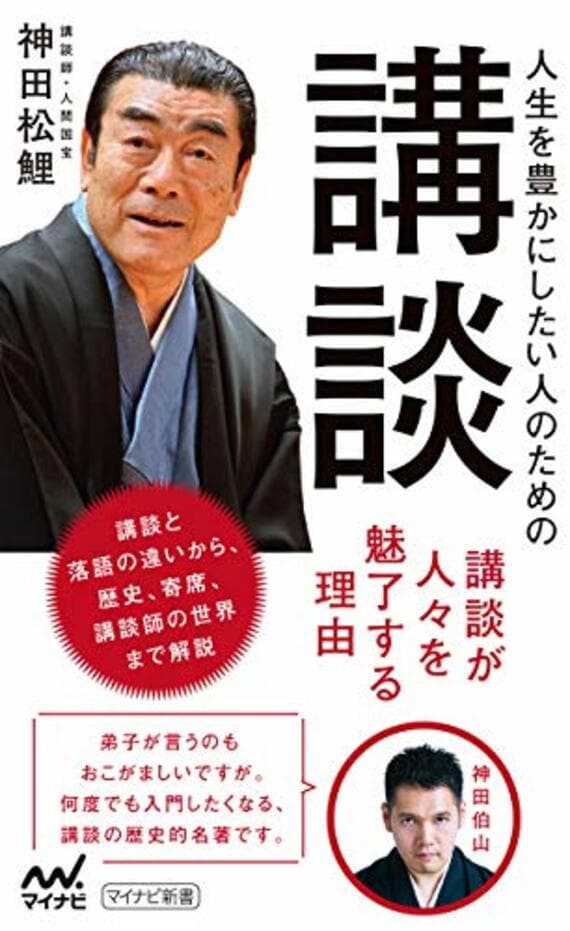
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら