
「東京藝大生」の努力のカタチに感動した
今回、僕は「東京藝術大学の学生と東京大学の学生との共通項」「藝大生と東大生の学び方の共通点」という記事を書こうと思い、実際に藝大生に取材してみました。
しかし結果として、僕はその記事を書くことを断念し、代わりに今回の記事を書くことに決めました。
その理由は、簡単です。心底「すげぇ」と感動したからです。
藝大生の方々に強いリスペクトを感じ、東大生と藝大生の共通項を書くより、シンプルに藝大生のすごさを語ったほうが価値があると考えたからです。
論理的・左脳的な考え方を極めた人が行くのが東大だとすれば、感性的・右脳的な考え方を極めた人が行くのが藝大だと言われています。
東大をはるかに超える10倍以上の倍率を誇る狭き門であり、しかも浪人率は7割を超えています。東大ですら浪人率は約3割なので、本当に東京藝大は受験の常識がまったく通用しない大学だと言えます。
そんな東京藝大という大学は、一体どういう場なのか? そして僕が「この努力は、本当にすごいな」と感じたのはどういうポイントだったのか? 今日はこの2点について、皆さんに共有したいと思います。

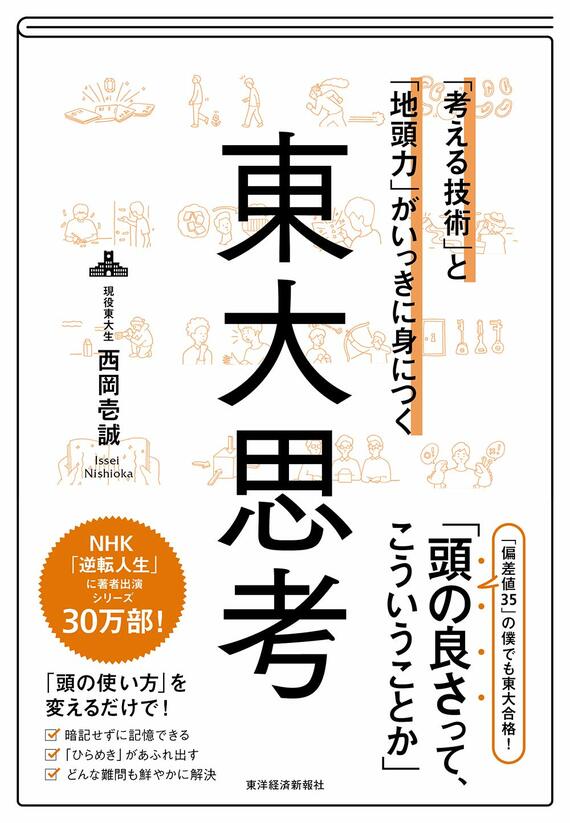































無料会員登録はこちら
ログインはこちら