通常のビジネスシーンでは、立て板に水のごとく、堂々とした話し方は説得力がありますが、謝罪のシーンでは逆効果になることもあります。ビジネスライクな話し方では「こちらの気持ちをわかってない」と思われてしまうかもしれないからです。
言葉を詰まらせる様子や、申し訳ない、情けないという気持ちでうまく話せない様子は、相手から見れば自分の痛みを理解してくれている、しっかりと反省している表現として伝わります。
「誤解を与えてしまい…」「そういうつもりでは」はNG
「そういうつもりではなかったのですが、誤解を与えてしまったようです」という説明は謝罪シーンでよく目にしますが、これは「自分は悪くないが、あなたが間違って認識した」と言っているようなものです。
謝罪となると責任問題が生じるため、弁解が増えてしまいがちです。謝ることによって生じる影響を恐れたり、責任を回避したいという気持ちが働いたりするのは自然なことではありますが、まずはぐっとこらえたほうが、その後の影響や責任が軽くなることが多いのです。
実際に、言いがかり的な理不尽なクレームへの対応となると、ついこちらの事情や意図を伝えたくなりますが、謝罪シーンでは怒りをおさめてもらうことを優先したほうが、ことの収束は早くなりますし、正当性を主張することでさらに関係が悪化することを避けられます。この場合には相手を不快にさせたことに焦点を絞ってお詫びをしましょう。
こう聞くと、ひたすら相手の言い分をのむだけで、こちらの事情は一切話せないのかというとそうではありません。次の解決策や再発防止策とセットで事情を説明します。
●Step4 事情の説明は対応策と再発防止策とセットで行う
事情を説明したくなる気持ちをぐっと堪えて、相手の気持ちに共感して詫びた後は、手土産である解決策と再発防止策の出番です。これらのセットで事情の説明を行うことで、言い訳と思われずに、経緯や事情を説明することができます。
例えば、先方の操作ミスが原因でエラーが多発しているような場合に、「操作ミスが予想以上に多くありまして……」と説明を始めたら、「こちらのせいにするのか!」と思われてしまうかもしれませんが、「〇〇の品質課題については、開発チームで全項目チェックを行い、原因を分類し対応を始めております。操作ミスが原因の課題については御社にも協力していただいてマニュアルを改定したいと考えていますが、いかがでしょうか」と再発防止策の提案の中に含めるのです。
解決策はできるだけ先方に協力してもらって解決していく提案がよいでしょう。謝罪関係から、共に問題を解決する協働関係になっていただくのです。互いに相手のほうを見ている関係から、目の前の問題を一緒に見る関係になれれば、収束に向かい始めます。あるプロジェクトではリカバリー本部を設置して、相手側のメンバーにも入っていただき、1つのチームとして活動することで、徐々に相手の怒りや誤解が解けていきました。
謝罪はできれば避けたいものですが、振り返ってみると謝罪を経験したプロジェクトのお客様とはそれまで以上に関係が深まり、今でも「あのときはお互い大変だったよね」と笑いあえる関係が続いています。マイナスからゼロを超えて、プラスに転じさせ「雨降って地固まる」を目指してみましょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

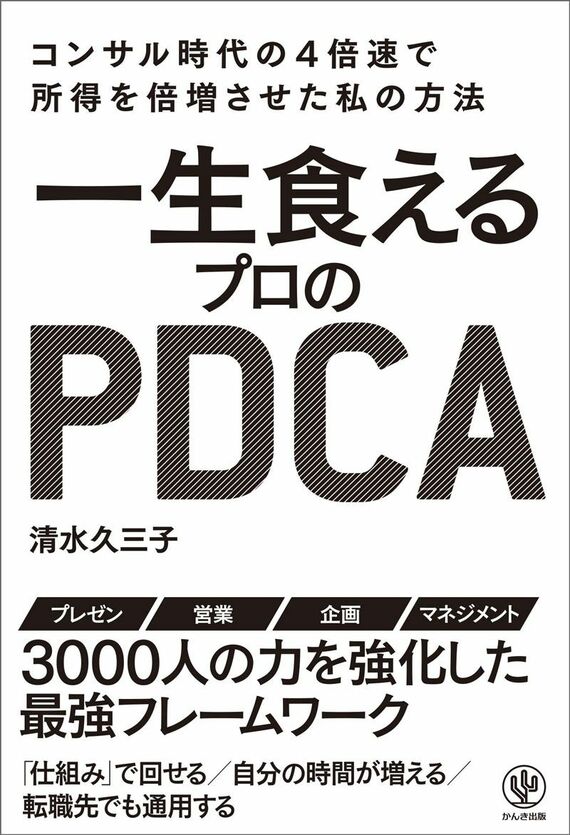






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら