55歳「孤独死」の危機から立ち直った彼の告白 妻との死別による悲嘆を救ったのは人だった
雪渕さんは、ハッキリとした口調で、こう答えてくれた。
「そんな自分がこんなことを率先してやっている、いちばんの理由は、この街の住人になりたいという思いからなんです。僕は、この街の住人の1人として生きて、死んでいきたいと思っているんです。異邦人じゃなくて、鷺沼に住んでいた雪渕さん(という人)がいたと近所の皆さんに覚えてほしい」
雪渕さんは、ふっと穏やかな目をリビングの網戸に投げかけた。そして、網戸を見ながら、「今、セミファイナルの時期じゃないですか」とふと思い出したかのようにつぶやいた。セミが最期の時を迎えるという意味らしい。
「ベランダに、セミがやってきて、ちょっと触るとジージーと鳴き出す。ひとしきり鳴いて飛んでいくから、あっ、死んでなかったんだなと思うんです。この前、またセミが止まったんですね。そして、また飛んでいくんだろうなと思ってたんです。そしたら、ジッジッジッと鳴いて、そのまま死んでしまったんです。その時思ったんですね、人間だけですね、つながりを求めてるのって。孤独死どうのこうと、大騒ぎするのは。昆虫とか、動物では当たり前のことですね、1人で生まれて、1人で死んでいくんですからね」
おひとりさまの理想の死とは
雪渕さんは、人が人間的な営みによって生かされていることを知っている。
雪渕さんの優しい目が私を捉えた。友人によく「中性的」と言われる雪渕さんは女性の友達のほうが多い。奥さんが亡くなってからは、「雪渕、ごはんちゃんと食べてるの?」なんて心配してくれる女性の友達もいる。今、雪渕さんはその世界を大切にしている。
「僕、この部屋が好きなんですよ。この部屋は、家内と最後に過ごした場所なんです。僕が親の介護で奈良に帰った時に、この部屋を残した理由は、戻る場所がないと自分が潰れちゃうからなんです。自分が安らげる場所だし、家内がいた場所でもある。ここに帰ってきたかったんですね。自分の最後の理想は、この景色を見ながら死ぬことなんです。これから訪問看護って増えてくると思うんですね。それで、友達とか後見人さんに、ちょくちょく来てもらう。それが理想ですね」
おひとりさまだから、孤独死防止のために、自らの身を守るというわけではない。ただ、自分が愛したこの風景とともに、友人たちや地域の人に愛されて、穏やかに、最期の時を迎えることが理想である。
私は、妻との死別や離婚がきっかけとなり、セルフ・ネグレクトに陥り、孤独死という結末を迎える男性を数多く見てきた。雪渕さんと、彼らとの違いはなんだろうか。実はそれは、とても紙一重であったのではないだろうか。
幸運にも、雪渕さんは、趣味の絵画を通じて、自らの悲しみに寄り添い、グリーフケアをしてくれる人たちに恵まれた。
「やはり、死別の悲しみを癒やすには、誰かにその体験を話すのがいちばん。それが私にとってはアート関係者だったんです」
雪渕さんは語った。かつては、地域や会社がその役割を担ってきたが、共同体が空洞化した現在、「悲しみを引き受ける」場所や人はもうほとんどないと言っていい。豊かな人間関係を持つ人に限られる、ぜいたくな希少品のようなものになっている。
サラリーマンは近隣関係が薄く、地域からも孤立する傾向にあるということが、平成19(2007)年度の国民生活白書では明らかになっている。特に長時間労働をしている人ほど、それは顕著らしい。
まさしく会社人間であった雪渕さんは、その傾向にピッタリ当てはまる。雪渕さんは、そんなサラリーマン生活で失った「縁」を、再びみずからの手で取り戻そうとしている。それがたまたま地域であったというだけだとも言える。
たとえば配偶者の死別が孤立の大きな要因となっている日本において、もっともっと、新たなグリーフケアをシステムとして確立できないだろうか。それがひいてはセルフ・ネグレクトや孤独死を予防する手段の1つにつながるからだ。自分の親しい人が亡くなったときに支えてくれるのは、雪渕さんのように、もしかしたら親族ではないかもしれない。
きっと、「縁」はなんでもいい。そして、それを切り開くのはいつでも遅くない。きっと誰にとってもいつから取り戻せるものだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

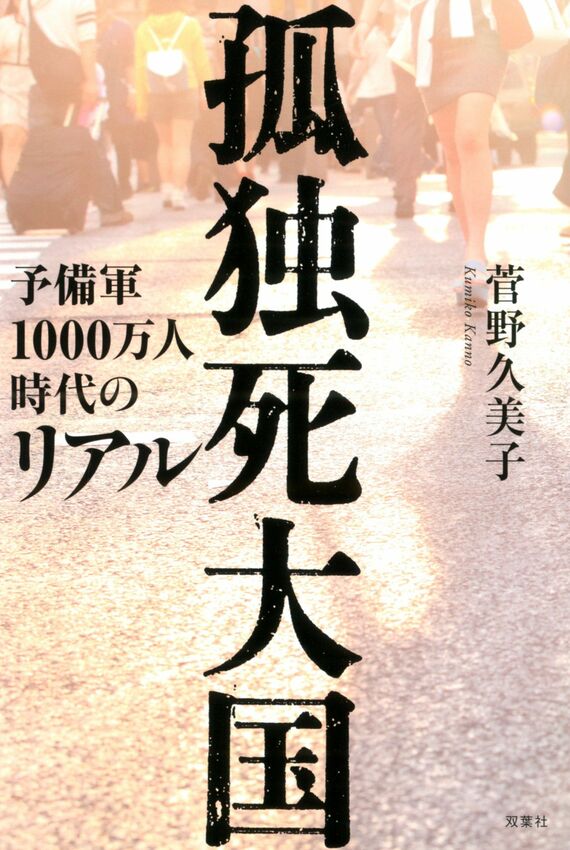
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら