その銀座の試写室というと、思い出す人が2人いる。
ひとりは作家の池波正太郎である。池波さんが「銀座百点」に連載していた「銀座日記」などを読むと、試写の帰りに銀座の気に入りのすし屋や天麩羅(てんぷら)屋に寄って軽く飲んだり食べたりしているところがよく出てくる。
ふらりと来て、お銚子を2本開けて帰っていった
たとえば、いまたまたま手元にある『日曜日の万年筆』には、こんな一節がある。
言うまでもなく、このとき池波正太郎はひとりである。
私が試写室通いを始めたとき、池波さんはすでに亡くなっていたから、試写室でお会いするということはなかった。しかし、このエッセイに描かれているような池波さんの姿を見掛けたことはある。
それは先に引用したのと同じエッセイの中で、池波さんが銀座の気に入りのすし屋として挙げている3軒のうちの1軒でのことだった。
私と友人とは、夕方のかなり早い時間にその店で待ち合わせていた。客は私たちだけであり、若い主人と気楽にしゃべりながら飲んでいた。そこに、ふらりと池波正太郎が現れたのだ。そして、若い主人とふたこと、みこと言葉を交わし、お銚子を2本空けると、出て行った。
私も友人も特に緊張はしていないつもりだったが、軽く会釈をして送り出すと、2人とも、ほっとしたあまり、つい話し声のトーンが高くなってしまったのがおかしかった。
池波さんには、ひとりでこうした店に入り、ひとりで飲み、食べるということに慣れている、独特の風格のようなものがあった。


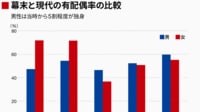




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら