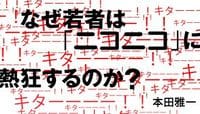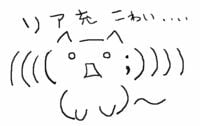5年後、日本のメディアコンテンツはこうなる 角川歴彦×川上量生対談(2)

川上:編集者って、ほんとに広義ですよね。たとえば、ジブリの鈴木さん(鈴木敏夫・スタジオジブリ代表取締役プロデューサー。川上会長はジブリの見習いでもある)は編集者ですよね。それに、角川会長も佐藤社長(佐藤辰男・KADOKAWA代表取締役社長)も、話をするとやっぱり編集者だなと思います。
編集者の能力って、世の中に必要な能力だと思うんです。何か新しいことをやるとき、特にコンテンツみたいな不定形なものを世の中に出そうというときは、編集作業は必ずいりますよね。
角川:「ネットになったから編集はいらない」なんて、とんでもないよ。
クリエーターが出てくる裾野が広がった
――出版なり映像なりのクリエーターのものづくりのやり方が、特にこの5年くらいで大きく変わってきた印象を受けますが、いかがでしょうか?
角川:いちばん大きな変化は、外部からクリエーターが入ってくるようになってきたことです。
これまで、映画の世界も出版の世界も、プロの脚本家、プロの俳優、プロの作家など、自分たちがプロのクリエーターだと思っている人に支えられてきたわけです。
でも、『カゲロウデイズ』(じん〈自然の敵P〉作のVOCALOID楽曲「人造エネミー」にはじまるマルチメディアプロジェクト。CD、ライトノベル、漫画、アニメなど多面的に展開している)の“じん”くんは、もともとニコニコ動画で出てきた素人ミュージシャンです。でも、彼が書いた小説『カゲロウデイズ』は1巻当たり50万部も出ています。本人にもお会いしたけど、50万部の作家には見えないです。川上くんの弟という感じで。