──温故知新に加え、「新たな資本主義モデル」も提示していますね。
「T字モデル」。実は入省3年目に執筆依頼があり、当時の考えをまとめたものの改訂版だ。いよいよ人口減少社会になり、一人ひとりが総合的な人間力で勝負していかなければならない。どういう人間を育てないといけないか、もう一度整理してみた。
──ほかにも人間力に着目したエピソードが小説を含め豊富に織り込んであります。
前述の渋沢栄一と西郷隆盛との面談のエピソードが何より面白い。渋沢がまだ若き役人だった頃のことだ。渋沢の正論に西郷は何も言わず、報復することもなく去っていく。政治家の陳情に渋沢は役人の立場からスジを通した。政治家と官僚のかかわり方をシンボリックに示している。明治時代にスッキリした政官関係もあったのだ。
──ベンダサンには空体語、実体語といった表現もあります。
憲法改正の話になるとまた同じような理屈で動くだろう。今も全然、変わっていない。しっかりこのキーワードの理屈を頭に置いて押さえておいたほうがいい。
空気の支配
──「空気」という言葉は今もよく使われます。
「空気」はなぜできたのか。米トランプ政権ができたのも、英国がEU(欧州連合)離脱を決めたのも、「空気」が動かしたからかもしれないし、中国の文化大革命もそうなのかもしれない。
──日本だけではない?
日本の場合は戦争まで行ってしまう。日本の「空気」はなぜ支配が強いのか。山本七平の文章はけっこう難解だから、原典に当たってみることだ。
──「水を差す」は出てこないのですか。
「空気の支配」に対して大事なのは「水を差す」。明治時代までは現実に引き戻す力を持っていた。
──同時に異端の人も大事と。
最後に立て直すのはそういう人たち。どこかにプールしておかないと、危機に対応できる人材がいなくなってしまう。
──ご自身は中国勤務以来、中国経済の研究をライフワークにしているそうですね。
この8月末に日中国交正常化45年のシンポジウムで話をしてきたばかりだ。中国は金融の自由化・国際化が中途半端な段階にある。これから激烈なバブルが起こる可能性もあると。もう一つ、経済のサービス化を本格化するのは、今のモデルでは無理があるとも伝えた。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

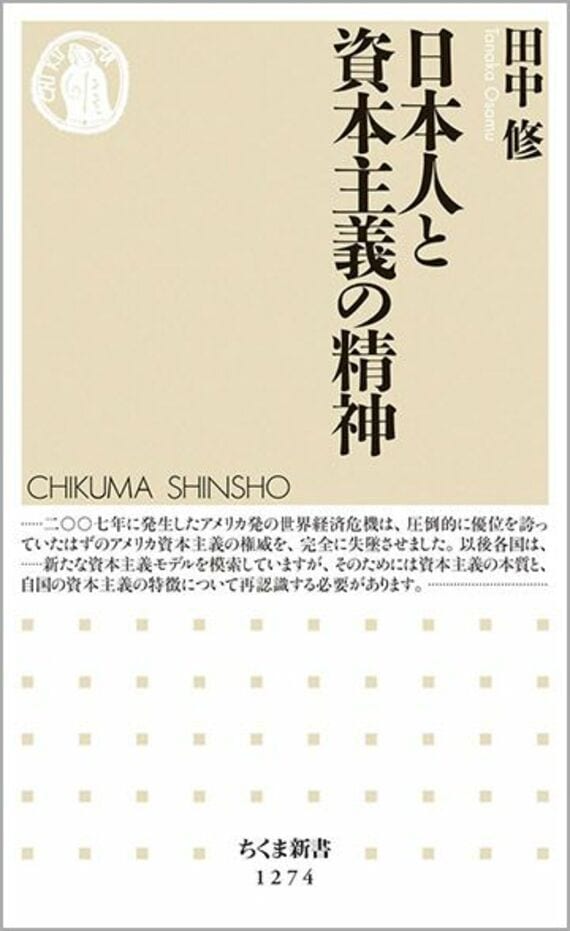






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら