「水平開きノート」を作り続ける町工場の底力 80歳の職人が手作業で1日1000冊を仕上げ
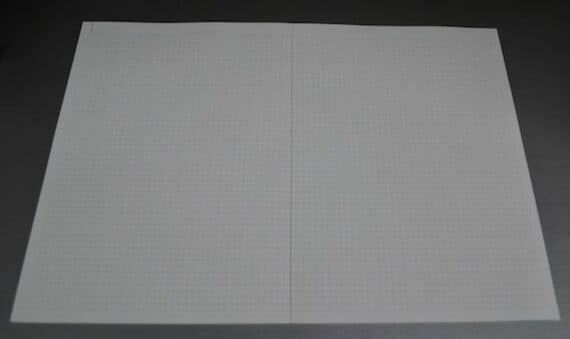
このノートには、日本の職人の技術の粋が込められている。
液晶テレビやスマートフォン、ゲーム機など中国で組み立てられているデジタル製品とは異なり、このノートの最終工程は日本でなければできないという。仕上げは「日本一の職人。できないことは何もない」(輝雄社長)という博愛さんの手作業で行っているのだ。アジア勢はもとより、日本人の他の職人にすら、まずマネができないという。
製本一筋の職人が持つ高い技術
80歳である博愛さんの生年月日は1936年の2月26日。当時の青年将校らが起こしたクーデター未遂の「2.26事件」が発生した当日だ。博愛さんの母は赤坂で彼を出産した時、近くで銃声が鳴り響くのを聞いた。
姓は輝雄社長と同じ中村だが、血縁関係はない。10代の頃から製本ひと筋で、非常に寡黙だ。中村印刷所とは40年来の付き合いだが、経営していた製本所が不況に押されて倒産、機械をすべて処分しようとしていたので、輝雄社長が引き取ったところ、「恩返しに金はいらないから手伝わせてくれ」と申し出て、アルバイトとして働いてきた。
社長と共同開発した水平開きノートの製法はこうだ。印刷後の二つ折りの紙を寸分たがわず重ね合わせた上で、背の部分に尖った器具で1ミリ以下の傷をつけ、そこに接着剤を二度塗りする。言葉で説明してもわかりにくいが、要するにきわめて精密な作業だ。
紙を重ね合わせる際に少しでもズレがあると、モノにはならない。現在のところ、模造品は出てきていないという。

博愛さんいわく、紙を寸分たがわず重ねられるようになるには「70歳過ぎ」まで修業しないと無理。人気に火がついたのを受けて1日あたりの生産量を300冊から1000冊に増やし、二つ折りの紙は外部からも調達するようになったが、重ね合わせと接着の最終工程は、今も彼1人で行っている。
これまでに4〜5人の職人が働きたいとやってきたが、紙をそろえる時点で挫折して去っていった。輝雄社長は重ね合わせた紙を手に「トントンさせてそろえようとすると、紙が微妙に変形してズレが生じる。間に空気を入れるのがコツ。いまの人たちは機械を使うのはうまいが、自分の手で紙をそろえることも、こうやって数えることもできない」と笑う。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら