新聞ですら間違えた「台湾問題」に対する日本政府の立場。「日本は台湾を中国の一部と認めている」と思い込む人たちの課題
こうした問題は匿名のSNS上の議論に限られない。台湾関連の情報を正確に把握することは、その分野を長年研究してきた地域研究者でさえ神経を尖らせる作業である。議論を活発に行うこと自体は、中国・台湾・日本のどこにとっても重要だ。ただ、残念ながら現在の日本では、自分に都合のいい台湾現地発の情報、あるいは中国のナラティブを鵜吞みにした情報発信がSNS上だけでなく大手メディアですらなされている。
例えば台湾の主要メディアがどのようなスタンスで報道しているのか、その背後にある歴史・人物・政治的文脈を理解しないまま、「自分の主張に沿っているから」という理由だけで「これが台湾現地の声だ」と思い込んで、そのまま議論を展開・拡散するのは危うい。また中国政府の主張があたかも事実であると鵜呑みにして情報を発信するのも危険だ。
これらの態度は、めぐりめぐって研究者や報道などが自らの「本業」に対する信憑性まで損ないかねず、十二分に慎重であるべきだ。実際、11月11日付の『東京新聞』の社説でも、今回の高市首相の発言について議論を行ううえでの論拠の扱い方に重大な問題があり、誤った言説が拡散され得る危険性を示していた。
東京新聞も誤った論拠で社説を掲載
東京新聞の社説「高市首相と台湾有事 存立危機を軽く語るな」で何が問題だったのか。それは中国が繰り返し声高に主張してきた言説を、そのまま疑問もなく受け入れ、この問題の根本的な前提を再確認しないまま、誤った論拠で物事を断じている点にある。
社説は高市首相に「言葉を選ぶべき」と答弁の問題を指摘した。その趣旨には筆者も賛同するが、社説内で触れられていた台湾問題に関する議論には問題もある。
例えば、「日本は1972年の日中共同声明で、台湾を中国の一部とする中国の立場を『十分に理解し、尊重』すると明記し、台湾を国家と認めていない」という記述がある。この書きぶりは、1972年の日中共同声明の一部だけを切り取り、そこから直線的に「台湾を国家と認めていない」と断定している点で、同声明への「読解力」を欠いている。
この社説と同様に日本では、「台湾は中国の内政問題なのだから日本が口を出すべきではない」という議論を持ち出し、そこで議論を強制終了させようとする言説もある。しかし、これも日本を含む各国が台湾問題をめぐり、ぎりぎりのラインを探りながら展開してきた「曖昧戦略」を自ら水の泡に帰す言説だ。
東洋経済オンラインに掲載された法政大学の福田円教授による論考(「アメリカ政府が『台湾地位未定論』を表明。『未定論』はアメリカの一貫した立場だが、今表明したのは中国の主張に対抗するため」)でも指摘されているように、「近年の中国政府は、サンフランシスコ体制および同体制と補完的な関係にあったアメリカや日欧など旧西側諸国との『一つの中国』に関する部分的合意に触れず、それに代わってカイロ宣言、ポツダム宣言、および国連の中国代表権交代を決めた国連総会第2758号決議を強調する形で台湾への主権を主張している」。



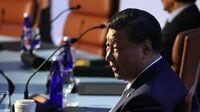



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら