新聞ですら間違えた「台湾問題」に対する日本政府の立場。「日本は台湾を中国の一部と認めている」と思い込む人たちの課題
これらの文書で実際に何が約束されてきたのか。中国が避けようとする「一つの中国」に関する部分的合意とは何か。歴史的経緯を振り返りながら確認したい。
1945年、終戦により日本の台湾統治は終わる。その前に1943年のカイロ宣言では、アメリカのルーズベルト大統領、イギリスのチャーチル首相、中華民国の蔣介石主席が共同声明を出し、「日本が中国から奪った領土(満州、台湾、澎湖諸島)は中華民国に返還されるべき」とした。これは戦後処理の方針表明であり、条約ではない。
日本は台湾の帰属先を明言しなかった
日本は終戦するにあたりポツダム宣言(1945年)を受諾する。これは日本の降伏条件を定めた文書であり、連合国が日本に対して「カイロ宣言の条項は履行される」「日本の主権の範囲は、本州、北海道、九州、四国と小さな島々に限定」と明記した。しかし台湾の地位に関しては、将来の平和条約によって最終的に決定されるとされた。つまり、台湾の法的地位は日本と連合国間の講和条約まで保留されたのである。
そして結ばれたのが1951年のサンフランシスコ平和条約だった。同条約には中華民国政府と中華人民共和国政府の双方ともに出席していない。国民党と共産党の内戦によって中華民国政府は台湾に撤退し、中国大陸では中華人民共和国政府が樹立され、どちらを正統な中国政府とするか連合国内でも意見が割れて、両方とも招かれなかったためだ。それもあり、サンフランシスコ平和条約は日本政府が台湾を「放棄する」とだけして、帰属先を明言しない形で結ばれた。
その後、1952年に中華民国と日本との間で日華平和条約が締結され、この条約によって両国間の戦争状態は正式に終結し、2国間の外交関係が樹立された。ただ、この条約の適用範囲は、中華民国の実効支配地域(台湾・澎湖)にのみに限定された。そして中華民国政府が台湾を統治する実態は認めているものの、台湾の帰属先は明言されなかった。
1972年には、上記の日華平和条約が終了し、日本と中華人民共和国との間で日中共同声明が出される。その中で「内政干渉」か否かを判断するうえで重要なのは、次の2点だ。
第2項の「承認する(recognize)」は法的な「政治承認」を意味する。問題は後者である。中国は「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する(reiterate:繰り返し述べて強調する)」とする。それに対して日本は「この中華人民共和国の立場を十分理解し、尊重し(fully understands and respects)、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としている。ちなみにここでいう「ポツダム宣言第八項」とは上記にも提示した「カイロ宣言の条項は履行される」「日本の主権の範囲は、本州、北海道、九州、四国と小さな島々に限定」という部分である。



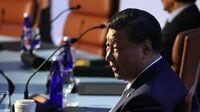



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら