新聞ですら間違えた「台湾問題」に対する日本政府の立場。「日本は台湾を中国の一部と認めている」と思い込む人たちの課題
ここであえて「認識する」と書かずに「アクノレッジ」と原語を示したのには理由がある。日本の外務省のサイトにおいても、この部分は単に「認識する」と訳されるのではなく、英語原文の「acknowledge」をそのまま示す形で紹介されている。単純に「認識する」とだけ書いてしまうと、本来の微妙なニュアンスである「支持も承認もしていないが、その立場を把握している」という距離感が伝わりにくいからだろう。
ここで再び先に問題があると指摘した東京新聞の議論に戻ろう。
「日本は1972年の日中共同声明で、台湾を中国の一部とする中国の立場を『十分理解し、尊重』すると明記し、台湾を国家と認めていない」と主張する場合、もし「日本国政府は、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認する」という部分を根拠に「台湾を国家と認めていない」と結論づけるのであれば、これも声明全体をきちんと読んで判断していないという意味で問題があるが、まだ議論の余地はあるかもしれない。
しかし、「十分に理解し、尊重する」の一文を根拠に「台湾を国家として認めていない」とまで言い切るのは、論拠としてはかなり説得力を欠く。すでに指摘したように日本は台湾の帰属先を明示しない形で戦後処理を進め、日中共同声明でもそれを踏まえているためで、台湾が国であるかの地位問題について触れていないからだ。条文を丁寧に読み、歴史的経緯を含む全体の文脈を踏まえれば、そのような短絡的な論の進め方はできないはずだ。
イデオロギーに沿った言説の拡散に危機感
今回の高市首相の発言は、従来の日本政府の立場を変えたものではないものの「曖昧戦略」から一歩踏み込んだものであり、今このタイミングで具体例を示す必要があったのかには疑問が残る。だからこそ彼女自身、すぐに「今後は特定のケースを想定したことを国会で明言することは慎む」と発言を修正した。アメリカにも同様の「踏み込み過ぎた発言」の事例があり、後に「従来の見解と変わらない」と火消しを図っている。そうした前例を考えれば、高市氏の迅速な修正は妥当な判断だったといえる。
今回、私がとりわけ遺憾に思ったのは、一部の左派・リベラルの言論が、日本政府自身の立場を踏まえずに、中国政府の主張をほとんど検証もせずに受け入れ、台湾のただでさえ狭い「国際的な空間」をさらに狭めてしまうことを手助けしていることである。日本の外交官たちが神経を尖らせながら練り上げてきた文言を雑に読み、そのうえで自分のイデオロギーに沿った言説が拡散していることに危機感を覚える。
台湾は、2300万人の生身の人間が暮らす場所だ。台湾人は、自らが獲得した自由と民主主義と人権を守るために、中国からの武力威嚇に備えざるを得ない状況に置かれている。リベラルが掲げる「普遍的価値」とは何なのか。いま一度、冷静に立ち止まり、台湾、中国に関するきちんとした知識を土台に、この議論を進めていくことを強く期待したい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



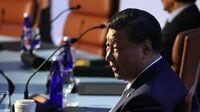



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら