
「毒矢のたとえ」に隠されたブッダの実践的な教え
ブッダの教えは『ヴェーダ』の土台の上に生まれたものだ。
『ヴェーダ』とは知識、知恵、悟りを意味し、インドに移住してきたアーリア人たちが長いあいだ語り継いできた文書だ。紀元前1500年前後にサンスクリット語で文章化されてきた。
ブッダは『ヴェーダ』の一部を取り入れながらも、批判的な視点を持っていた。業や輪廻、解脱という『ヴェーダ』の基本的な世界観は引き継いだものの、固定で不変の自我――アートマンと呼ばれる意識の主体のようなもの――を認めなかったのだ。ブッダは「無我」を説いた。
「無我説」は、自分のなかに不変の実体があると考える『ヴェーダ』の思想とは区別される、仏教固有の思想だといえるだろう。
けれどよく考えてみると、無我説はある意味で論理的ではないようにも思える。それは仏教が「無我説」を主張する一方で、『ヴェーダ』の「輪廻説」を受け入れているからだ。




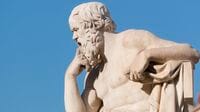



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら