一方で、がん末期や慢性的な重度難病の終末期、脳梗塞後の安定期、老衰状態などではさまざまな変化が起こりますが、その変化に対して病院だからといって「万全」の治療やサポートができるわけではありません。
病院では、医師をはじめとする医療・介護の体制は、基本的に「治すこと」に特化した組織になっています。そのため、変化に対して「治すこと」を前提とした標準医療を行います。
その人らしく過ごせるために
「治すこと」が悪いわけではありません。ただ、「治らない」状態なのに「治そう」とすることで、苦痛を生んだり、いのちを縮めたりすることが少なくないのです。
終末期の患者さんには、日常において医療的なケアと介護的なサポートを続けていれば、「急性期の変化」はほとんど起こりません。
患者さんやご家族に起こりうる変化についての説明がていねいになされていれば、それはすべて想定内の変化。
看取りが近い状態で大切なのは、変化が起こったときに「標準治療」をすることではなく、その患者さんの苦しさや痛みを取りながら、穏やかにその人らしく過ごせるためにどのような薬を出して、どのような介護体制を行うかなのです。
それは「治すための標準治療」の枠に収まるものではありません。
自宅では本人やご家族と人間的なコミュニケーションをとり、何でも言いやすい環境で薬をこまめに調整したり、介護的な環境を細かく調整するなど、「個人に応じたカスタマイズ医療」ができるのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

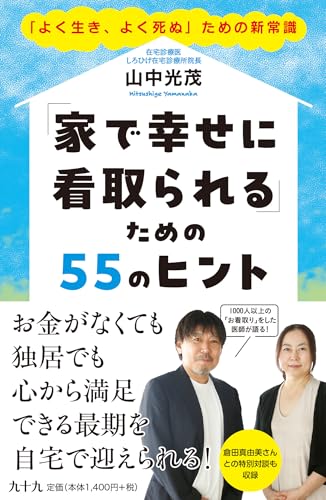






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら