ビジネス書の読み方は通用しない…『論語』に挑戦するも途中で挫折した人に教えたい"3つの誤解"
ただ、すべての本に適用できるわけではない。
前述の通り、『論語』が今のスタイルでまとまるまでには、多くの時間と人間が関わっている。当初から意図的に、論理的に構造化されたような書物ではなく、「事後的に、結果的にこうなっていった」というのが実態だ。
たとえば、『論語』の冒頭の3つの「篇」(通常の本における「第1部」「第2部」のようなイメージ)のタイトルを確認すると、「学而(がくじ)」篇、「為政(いせい)」篇、「八佾(はちいつ)」篇とそれぞれ記されている。
現代的な理解の仕方では、「第1部が"学び"について、第2部は"政治"について書かれているのだろう、はて第3部は?」という読み解きになってくるだろうか。
各篇のタイトルはキーワードになっていない
実際、確かに「学而」篇は学びについての章句から始まる。ちなみに、「章句」とは『論語』内の一塊の文の集まりのことだ。全部で約500章句ある。
ただ、「学而」篇が一貫して学びについて「だけ」書かれているのかというと、必ずしもそうはなっていない。次の「為政」篇も同様だ。
種明かしをすると、各篇のタイトルは、単に冒頭の章句にある漢字2文字を取って付けているだけに過ぎない。「その篇を貫くキーワード」というわけではないのだ。
したがって、目次をじっくり眺めて「全体構造を把握しよう」「各篇に書かれていることを鳥の目で俯瞰的につかんでやろう」といった本の読み方を『論語』に当てはめると、あっという間にストレスだらけの読書体験になってしまう。
だからこそ、あらかじめ「そんな読み方をしてはいけない」という、本稿のようなガイダンスが有益となるわけだ。
ファストで、効率的な読書スタイルでサクッとなんとかしてしまおうという読者に多数出会ってきたからこそ、こうした処方箋をこの段階でしっかり提示しておきたい。


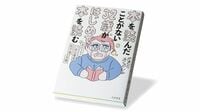





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら