ビジネス書の読み方は通用しない…『論語』に挑戦するも途中で挫折した人に教えたい"3つの誤解"
「孔子の身長2メートル以上」説も、確かに『史記』にそのような記載はあるが、せいぜい「平均よりは長身だった」というくらいだろう。
また、『論語』は漢字の集合体であり、読む人によって多種多様な解釈が可能だ。その結果、どこまでが本当に孔子の言ったことなのか、その発言の意図や解釈の妥当性まで踏まえると、いよいよ真偽を確かめることなど困難になってしまう。
以上をまとめると、孔子という1人の著者が、一貫して主張していることを読み取ろうといった読書スタイルでは、『論語』は決して心地よく応答してくれない。
これから『論語』に触れる際の大前提として、どうか真っ先にこのことをわきまえておいてほしい。多くの現代人が素朴に「読書とはこういうものだ」と思っている読み方では、『論語』とは付き合えないのだということを。
1ページから最終ページまでを順番に読み進め、著者の一貫した主張を読み取るといった読み方をしても、『論語』は応えてくれない
「『論語』には論理的な構成がある」という誤解
もう1つ、ビジネス書にばかり触れてきた人が、とくに陥りがちな誤解がある。
「本文を読み始める前に目次を見て、本の構成や構造を効率的につかむ」といった読書のノウハウ、テクニックを、『論語』のような古典にも当てはめてしまう。
これで果たして、『論語』の構成や構造をつかむことができるのだろうか。
実際、ビジネス書であれば、確かにこの読書の技術は役に立つ。ビジネス書でなくても、ロジカルに構成されている本であれば、どのジャンルであっても目次から本の全体構造を把握することは可能だ。
つかんだ構造・構成を地図とし、常に全体像を見失うことなく本を読み進めていけば、効率的で、それでいて深い認識にも至れるような読書が可能になる。


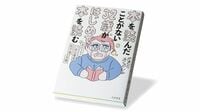





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら