ビジネス書の読み方は通用しない…『論語』に挑戦するも途中で挫折した人に教えたい"3つの誤解"
確かに、受験問題の長文読解はこの方法で概ね対処できるし、だからこそ、学生時代にこうした読み方に関するトレーニングもしてきたのだろう。
しかし、これは決して「唯一の本との付き合い方」ではない。にもかかわらず、どんなタイプの本にも同様の読み方を適用し、「どうにも読めなかった」「よくわからなかった」といった感想に至ってしまう……。
これまでに出会ってきた社会人学習者の大半が、こうした読書スタイルしか持ち合わせておらず、これをそのまま『論語』にも当てはめてしまった結果、早々に挫折するという読書体験に陥っていた。だからこそ、この話は『論語』を読むためのガイダンスとして有効なわけだ。
再度確認すると、「典型的な本との付き合い方」とは、「著者が繰り返しているメッセージ=主張をつかむこと」をベースにした読解法を指す。
しかし、たとえば「著者が複数人いる」場合はどうだろうか。あるいは、「作者の死後、もはや本人もあずかり知らないところで本ができあがる」といった成立過程の場合、その書物の「著者は誰」ということになるのだろうか。
そもそも孔子自身に執筆できるはずがない
「『論語』の著者は誰か?」と問うと、大半の人は「孔子」だと答える。しかし、『論語』の著者は孔子ではない。孔子の死から数百年後に成立している以上、孔子自身に執筆できるはずがないのだ。
『論語』は孔子が亡くなった後、直弟子や孫弟子、そのまた弟子や門人、時の為政者たちによって、数百年かけて少しずつ今のカタチに収斂していった。
単独の作者がいるわけではないし、編纂に関わった人間の多くが、同時代人ですらない。時間軸が100年単位で異なっていれば、時代背景や価値観も変わって当然だ。
正直、捏造や創作もあれば、『論語』や孔子を権威付けたい人たちによって「話が盛られている」ケースすらある。動画による講義やリモート授業がない時代に、「弟子3000人以上」はさすがに現実的な数だとは思えない。


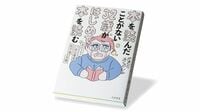





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら