「人生後半の充実度は"腎臓"で決まる」→身体にとって「万能薬」となる簡単な習慣とは
つまり、子どものころに大人からしつこく言われた「腎臓によくない」は、「いつも通りの日常を送れなくなってしまう」ということであるわけだ。当時はそんなふうに理解できていなかったはずだが、いまからでも意識するべきことではあるだろう。
腎臓の常識は大きく変化している
しかも当然のことながら、他の臓器と同じように腎臓の機能も加齢に伴って少しずつ低下していく。そして働きが落ちると、「いつも通り」にできていたはずのことができなくなっていくのだ。
たとえば腎臓病や人工透析のリスクが高まるだけでなく、疲れやすくなって体力が続かなくなったりするという。また、動脈硬化や心臓病、脳血管疾患など重大な病気のリスクも高まるらしい。腎臓の衰えを契機として、さまざまな病気や全身の老化が加速するということだ。
そう聞くとさらに恐ろしくなってしまうが、必要以上に悲観的になる必要もなさそうだ。やるべきことをしっかりやれば、腎臓の機能低下は防ぐことができるからである。さらに“やるべきこと”をきちんとやって腎臓の機能をキープしていけば、体の不調やトラブルを防ぐことができ、病気の進行や老化を防ぐこともできるのだ。
しかしそれ以前に、私たちが信じている“常識”の多くは、必ずしも正しいとはいえないようだ。時代の変化とともに、「腎臓病の常識」も大きく変化しているからである。
冒頭で触れたことにもつながるが、たしかに腎臓病にはひと昔前まで、特別な目で見られがちな側面があった。「腎臓が弱い人は運動ができない」とか、「腎臓病の人は疲れやすいので、他の人と同じように仕事をすることができない」「食べたいものも食べられない」、さらには「腎臓病はいったん悪化したら、もうよくならない」など。















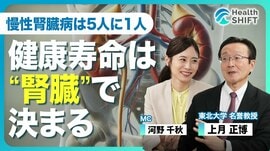






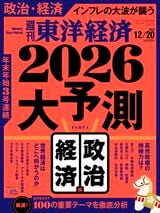









無料会員登録はこちら
ログインはこちら