それに、じつは人のネフロン数はかなりの個人差があります。「2つで200万個」というのはあくまで平均値であり、少ない人であれば腎臓2つで50万個、多い人であれば腎臓2つで300万個……。もっとも少ない人ともっとも多い人とでは10倍近い差があるとも言われているのです。
どうしてこんなに大きな差が出るのか。遺伝などさまざまな要因が影響するとされていますが、なかでもとりわけネフロン数への影響が大きいとされているのが「出生時の体重」です。
これは、生まれたときの体重が重い人ほどネフロン数が多く、逆に低体重で生まれた人はネフロン数が少ない傾向があるということ。未熟なままの低体重で生まれた場合、腎臓のネフロンが未完成状態であることが多いんですね。
すなわち、低体重で生まれた人はネフロン数という点では最初からハンデを背負っているようなもの。通常よりも早い段階でネフロン数が底をついてしまう可能性があるため、心当たりがある人は、その分、できるだけ腎機能を低下させないように注意を払っていかなくてはなりません。
元気なネフロンを温存するシステム
もしネフロン数がゼロになって濾過機能が完全にストップしてしまったら、人間はもう生きていけません。老廃物や毒素を含んだ血液が全身を回り、尿毒症になって死んでしまいます。どうにか生きたいのであれば、ネフロンがゼロになる前に人工透析や腎移植などの措置をとるしかありません。
もっとも、腎臓はかなりネフロン数が減少してもすぐに命に関わるような事態にならないよう、かなりの「予備力」を用意していることが分かっています。
それというのも、ネフロンは、弱って死にそうなネフロンから先に使われて、余力のあるネフロンや元気なネフロンを備えとして温存しておくシステムになっているのです。大まかに「最前線で酷使されていまにも死にそうなグループ」「時々使われてまだ余力を残しているグループ」「まったく使われていない新品状態でピンピンしているグループ」の3グループに分かれていて、死にそうなネフロンのグループから順に使われていくわけです。
このため、腎機能がだいぶ低下してきたとしても、すぐに腎不全に陥るようなことはありません。たぶん、生命機能維持に重要な臓器であるため、すぐに機能停止してしまわないシステムになっているのでしょう。だから腎臓はゆっくりと悪くなっていく。それこそ何十年という時間をかけてじわじわと少しずつ衰えていくものなのです。





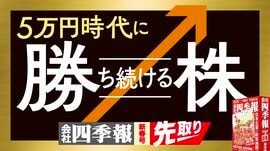








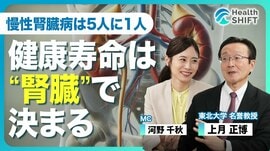







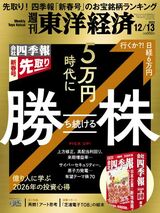









無料会員登録はこちら
ログインはこちら