あなたの脳がどんどん"退化"するAIのダメな使い方 脳科学者・茂木健一郎さんが語る"AIの今"
では、生成AIによって生成された文章をレポートや論文として提出することで、いったい誰が得するのでしょうか。
ラクに単位をとれたり、ラクに卒業できる学生でしょうか。
いいえ、私はそうは思いません。
たしかに、生成AIを使ってレポートや論文を提出すれば、そのときはラクできるかもしれません。
ですが、よくよく考えてみれば本来、レポートや論文の作成に取り組むという作業には、物事を調べ上げ、さまざまな情報の中から有益な情報を取捨選択し、文章を紡ぎ出す力が身につくという学習効果があります。AIに頼りきってしまえば、それを放棄することにつながります。
そうした能力を身につけないまま卒業し、社会に出てしまえば「あいつは文章一つもろくに書けないのか」という厳しい評価が待っているだけでしょう。
また、大学側の先生たちにとっても得などありません。学生たちの学習成果を正しく評価することを困難にし、公正な成績評価を妨げるだけでなく、学生が生成AIを利用してレポートや論文を作成する可能性がある以上、先生としてそれを見抜くことに多大な時間と労力を割く必要があるからです。
そうなれば、「AIなんて誰の役にも立てていない」ということになってしまいます。
「脳+AI」の共生によって脳を覚醒させる好例
では、そうしたAIアライメントを考える上で日本が世界に誇るアニメ業界の最新事例を紹介しましょう。
日本のアニメは世界中で視聴され、多くのファンを持っているという強みがあるのは誰もが認めていることでしょう。日本のアニメの魅力とすごさは、緻密なストーリーや個性あふれるキャラクター設定、そして美しいアニメーション技術だと私は考えているのですが、そうした日本のアニメ業界において、一つ大きな問題が深刻化しています。
人材不足です。
作品にもよりますが、30分間のアニメ1話分でおよそ4000枚の作画が必要であり、1枚を完成させるのに数時間かかることもあるそうで、そうしたアニメーターの数がコンテンツ数と比較して絶対的に足りていないのです。
このような課題を解決するために、アニメ制作の現場でもAIの導入が始まっており、実際にNetflix の短編アニメ『犬と少年』では、背景画の部分において画像生成AIが活用されました。
このようにAIによる作業効率化を図ることで、より多くのアニメが世の中に送り出され私たちを楽しませてくれるだけでなく、AIにはできない創造性あふれるアニメーターを増やしていくことにもつながっていく。まさに、「脳+AI」の共生によって脳を覚醒させる好例と言えるかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

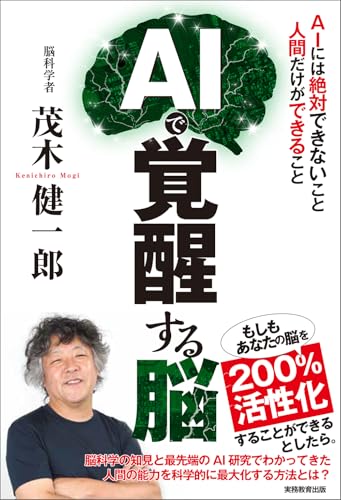






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら