パワハラに怯えて指導ができない=「物言わぬ上司」になる人とならない人の明確な差
かつては、スポーツの世界などで「勝利至上主義」がまかり通っていました。指導者の言うことが絶対で、練習中に水を飲んではいけないといった、今では考えられないような「正しさの押し付け」が横行していた時代です。しかし、時代は変わりました。そんなことをしていては、人は育たないのです。
真の「指導」とは相手の主体性に火を灯すこと
では、パワハラと対極にある、真の「指導」とはどのようなものでしょうか。
それは、相手の「主体性」に火を灯す関わりのことです。そもそも教育の目的とは、「人格の完成」を目指すことにあるはずです。人を育てる、育成するということを考えた時に、最も大切なのは、本人が「自分のためにやる」という状態をいかにして創り出すか、ということです。
一昔前は、指導者が絶対的な「正解」を持っていて、その言う通りにできる人間が良い部下、良い生徒だとされていました。しかし、その時代はもう終わったのです。
2023年の夏の甲子園を制した慶應義塾高校の森林監督もそうですが、今の時代に求められる指導者像は、大きく変わってきています。それは、一方的に答えを与えるのではなく、「考えさせて、最も良い方法を自らが自分の責任で選び、成果を出す」というプロセスをサポートする存在です。
私たちが長年サポートさせていただいている花巻東高校では、毎朝授業が始まる前に「ホームルーム」という時間が10分間あります。生徒たちは「立志夢実現プランナー」という手帳を開き、自分の人生の目的や意味を考えることから一日をスタートさせるのです。そうすると、彼らのスイッチが入る。「先生のために」ではなく、「自分のために」勉強するようになる。やらされ仕事ではなく、自分ごととして捉えるからこそ、主体性が生まれ、とてつもない成果に繋がっていくのです。

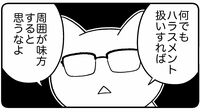






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら