「忘れ物がないよう持ち物をチェック」はNG?恋愛関係の構築がうまくいかず、最終学歴も低い傾向…子供の「考える力」を奪う親の行動とは
NG行動3『指示・命令型のかかわり』
親が家庭で常に指示を出し、子どもがそれに従っていれば、一見家庭内の秩序は保たれ短期的な問題行動も減るかもしれません。「これをしなさい」「あれはダメ」と細かく命令すれば、子どもは指示の範囲内で動くため親の不安も和らぐでしょう。強く叱責したり罰を使ったりすれば、その場では子どもを従わせることができ、親の望む行動を取らせやすくなります。
しかし指示や命令によって子どもを動かそうとするときに「考えている」のは誰でしょうか。考えているのは「親」であり「子ども」ではないことに気づく必要があります。
私は保護者向けの講義の中でいつも「指示・命令型の親がその関わり方を変えずにいると間違いなく考える力がない子になります」と強く警告しています。
指示・命令型の家庭で育った子は自己決定の経験を積めないため、成長して親の管理から離れた途端に何をどうしてよいかわからなくなるケースもあります。
心理的に抑圧された環境が長いと、反動で思春期以降に反抗的・攻撃的な行動に出たり、萎縮して他者に流されやすくなったりするリスクも考えられます。実際の社会では正解のない問題や選択が数多く存在します。
親の命令に従うだけではなく、「なぜそれが必要なのか」「自分はどうしたいのか」を考える訓練を積ませなければ、子どもはいざというときに自分の頭で判断できません。指示・命令型の養育は一時的な統制にはなっても、将来的に必要となる思考力・判断力を育むことを阻害するという点で大きな問題と言えます。
では、子どもの「考える力」を伸ばすために親は具体的にどう行動すればよいのでしょうか。シンプルに上記の3つのNG行動の逆をやってください。
すぐに答えを教えるクセをやめ、代わりにヒントを出したり一緒に問題を読み解いたりして、子ども自身が「わかった!」と気づく瞬間をつくってください。たとえば「次はどうすればいいと思う?」「どうしてそうなるのかな?」と問いかけるだけでも、子どもの頭は回転し始めます。
子どもが自力で考え抜いた末に答えに辿り着いたときはしっかり「自分で考えたこと」を褒めてください。そのプロセスこそが思考力育成のトレーニングです。スタンフォード大学のオブラドヴィッチ教授も「親が子どもに主体的にやらせることで、子どもは自己抑制力を練習し自主性が育まれる」と指摘しています。
親は答えを知っていてもあえて口を出さず、陰で見守る「黒子」に徹するくらいの姿勢が理想です。

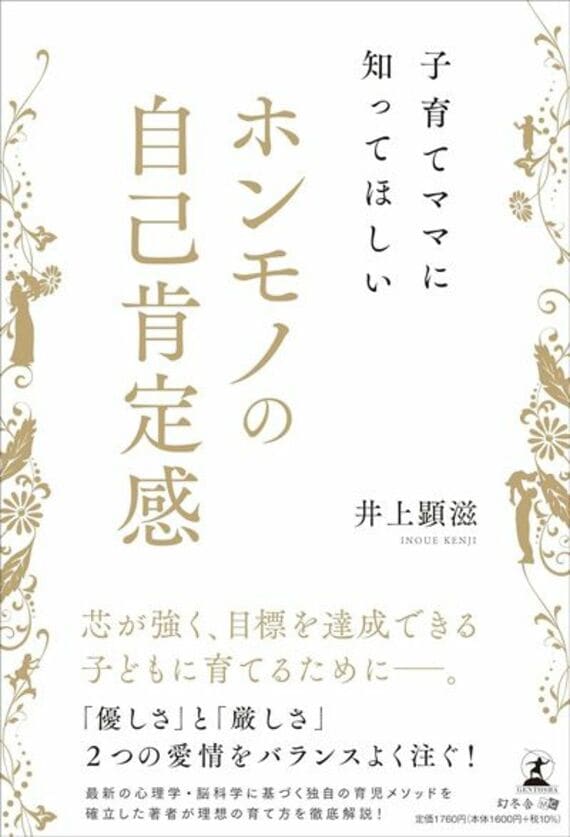
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら