「コハウジング」を選択する人が増えている理由、コミュニティー意識が高まるものの共同生活ならではの難しさも
例えば、チューリヒ西部で進められているクラフトベルク1の新プロジェクトでは、クラスターフラットの1人当たり面積は平均約34平方メートルで、同じ開発内の一般的なアパートの32.5平方メートルよりわずかに広い。ただ、いずれも市全体の平均を下回っている。

同プロジェクトはコッホ地区にあり、最大10の寝室を備えた非クラスター型のコハウジング住戸や、「ローバウ(大まかな建物)」と呼ばれる8戸の住居も含まれている。これらは4メートルの高さの天井を備えたコンクリートシェルとして引き渡される予定で、バスルームとキッチンのみが設けられ、あとは居住者がレイアウトを担うことができる。
この建物を設計したチューリヒの建築事務所スタジオ・トラクスラー・ホフマンの建築家、ノエミ・エンゲル氏は「空間的なゆとりがあり、多くの可能性が広がる」と話す。
柔軟な未来
チューリヒの建築士、モリッツ・ケーラーさんはこの開発プロジェクトにある6戸のクラスターフラットの一つに注目している。それぞれ最大12人が暮らす想定で設計されている。
ケーラーさん(29)は現在、市中心部で2つの寝室がある集合住宅に割安な条件で住んでいるが、クラスターフラットからもたらされる強いコミュニティー意識に魅力を感じているという。ケーラーさんと現在のルームメートは、来年入居開始予定のコッホ地区の住戸の一つに申し込むため、仲間を集めている。
ケーラーさんは同僚の多くが結婚して家庭を築くのを目にする一方で、もっと柔軟なライフスタイルを望んでいる。従来のスタイルは「あまり現代的とは思えない」といい、クラスターフラットであれば、「柔軟な未来に対応でき、いつかボーイフレンドと一緒に住みたいと思うかもしれないし、子どもを持ちたいと思うかもしれない。そんなときにも、引っ越しを何度も繰り返さずに済む」と語った。
(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)
著者:David Rocks、Levin Stamm
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

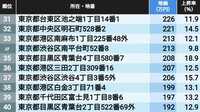































無料会員登録はこちら
ログインはこちら